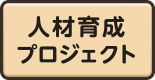2025年10月31日(金)研究会 議事録
第5回研究会
2025年10月31日 15:00‐18:00
於:京大吉田キャンパス本部構内「法経東館」地下 1 階 三井住友銀行ホール
登壇者:竹内昌義(東北芸術工科大学 デザイン工学部 建築・環境デザイン学科 教授)
小野寺弘晃(国立環境研究所 社会システム領域 地域計画研究室 研究員)
第5回研究会では前半に、東北芸術工科大学で研究に取り組む竹内昌義先生より、欧州の脱炭素の取り組みや建築物の断熱の取り組みについて報告がなされた。後半には、国立環境研究所の小野寺弘晃先生より、脱炭素化と地域の持続可能性の両立に向けたエネルギー転換の空間戦略について報告がなされた。
「エネルギーから暮らしをデザインする」
竹内昌義(東北芸術工科大学 デザイン工学部 建築・環境デザイン学科 教授)
私が所属する建設設計事務所「みかんぐみ」は現在4人体制であり、30年ほど前にNHK長野放送局のコンペで最優秀賞を獲得し、設立された。商業施設や学校のデザインに携わっており、最近では東京の万世橋高架下のリノベーションプロジェクトや大阪万博のルクセンブルクパビリオンのデザインに携わった。
私は福島の原発事故を契機に、脱原発や再エネ導入が次世代の人のために必要性であると強く思うようになった。私の専門分野は建築であり、環境省の分類では業務と家庭に関係する。日本は温暖な国であり、比較的エネルギー使用量が少ないと思っていったため、業務と家庭で日本のエネルギーの三分の一を消費しているということを初めて聞いた時は驚いた。しかし、この分野に関しては2050年までの脱炭素が技術的に可能であると思っている。
脱炭素の取り組みは「儲かるからやる」という考えがベースになければ、進んでいかないと思っている。この考えがベースにあるヨーロッパでは脱炭素が進んでおり、日本で脱炭素が進まないのは「脱炭素は地球のためにやらなくてはならない」と考えられているためだと思っている。例えば、住宅に太陽光パネルを5kW載せるのは、現在では1kWあたり20万円ほどなので100万円ほどである。つまり、年間電気料金を10万円支払っている場合、10年で元が取れることとなる。太陽光パネルは20年から30年使えるため、利用した方が得となる。
資源エネルギー庁は主要国の発電電力量に占める再エネ比率の比較をしているが、これを確認すると、ドイツやイギリス、スペイン、イタリアはいずれも再エネが4割を超えており、原子力の割合が高いフランスでも2割を超えている。一方で、日本とアメリカは2割を下回っており、いかに遅れているかがよくわかる。日本はUAEでのCOP28にて、2030年に再エネを三倍にするという目標を掲げた。しかし、2024年には過去最高の成長ペースで再エネが導入されたものの、それでも目標には間に合わない状態である。高市首相はメガソーラーをやめると言っているが、その帳尻をどのようにして合わせるのか。この点について日本の記者は誰も問いかけず、政府も答える気が無いように思われる。日本政府は二枚舌の状態である。
一方で、再エネ導入が急速に進んでいるのは事実であり、最大の要因は低価格化だと私は考えている。かつては住宅用太陽光パネルに数百万円を支払っていたが、現在では先ほど話ししたように100万円ほどである。100万円を定期預金に入れた場合、ほとんど金利はつかない。再エネ導入をやらない手はないと考えられる。
海外事例に目を向けると、例えば、コペンハーゲンでは再エネの割合が7割を超えており、2030年には脱炭素化する。コペンハーゲンではごみ焼却場でコジェネをおこない、熱を市全体に供給している。また、郊外にあるロラン島では風力発電に力を入れている。私は十数年前、そして3年ほど前にコペンハーゲンを訪れたが、太陽光に関してはそれほど増えたという印象は受けなかった。しかし、見た目が変わっていなくても、北欧や中欧では脱炭素がかなり進んでいる状態である。
建物を利用中にどの程度エネルギーを利用しているのかについては日本でもチェックされているが、北欧では建設時と取り壊す際にもCO2排出量がチェックされる。そのため、新しい材料がなかなか使えず、特にコンクリートと鉄が使えなくなってきている。そのため、材料のリサイクルがおこなわれており、例えば、ビール工場の壁を新築の壁に活用した建物が見受けられる。また、古い窓と新しい窓を組み合わせて作られた斬新な窓を有する住宅も見受けられる。
デンマークは断熱に力を入れているが、いつから取り組んでいるのかを聞くと、オイルショックのあった1970年代からという答えが返ってくる。一方で、日本の断熱における義務化は1995年である。また、日本の住宅のエネルギー利用は100kWh/m2ほどであるが、デンマークでは15kWh/m2であるパッシブハウスに近づいている。つまり、デンマークでは多くの人がほとんど暖房費のかからない住宅に住んでいるのである。1970年代にエネルギー基準を制定できたのは、建物を断熱し、エネルギー効率が良くなると化石燃料を購入しなくてもよくなり、その分の代金を補助金に回すのがよいという考えが共有されたためである。また、私は「やってみたら結果的にうまくいったから、もっとやろう」という感覚もデンマークの断熱を促進したと考えている。そして、近年日本でも取り組みがあるが、省エネ性能の等級ラベルを設定しており、どうすればさらにエネルギー消費を減らせるのかがわかりやすく示されている。そのため、専門家でなくてもどのように断熱を進めればよいのかがわかるようになっている。また、等級が高くなり、家賃を高く設定しても借り手が見つかる状態である。
デンマークはカーボンオフセットにより2045年までに1990年比で温室効果ガスの100%削減が可能である。2050年の10%の削減分は他国に売ることとなり、これが日本が買うとなると、デンマークは何もしていないの日本からお金を得られることとなる。
ドイツに関しては、石炭を所有しているもののそれを使わずに再エネに注力している。日本は石炭をわざわざ買ってまで石炭火力に固執しており、ドイツには日本の姿が異様に映っていると思われる。また、ドイツでは2016年時点ですでに太陽光と風力の発電が需要を大きく上回っている時があり、私はそれに対する問題意識がEVの波を創り出したと考えている。しかし、EVを推進すると国内産業が衰退し、中国製のEVが大量に流入する恐れがあるため、EV推進に慎重になっているのがドイツの現状だと思われる。建物に関しては30年ほど前から既にパッシブハウス住宅が建てられており、非常に進んでいる状態である。
フランスでは自動車を使わずに徒歩での移動を推進する都市政策がおこなわれている。日本では脱炭素に関して自動車の技術的な話が盛んであるが、フランスではそもそも自動車を使わないという流れが主流である。パリには広場がたくさんあるため、自動車は片側車線でしか走行できず、残りは歩行者と自転車のために使われている。セーヌ川沿いのかつて高速道路だった場所も現在では歩行者と自動車のための道路となっている。
日本が脱炭素をすれば化石燃料を買う必要がなくなる。日本は毎年、化石燃料に20兆円から30兆円を支払っているが、この代金を別の用途に使えるようになる。地域においても域外流出が無くなり、経済的に豊かになる。エネルギー代金流出により、地域が不安定になっているのは全国的な問題である。例えば、私がよく訪れる岩手県の紫波町では800億円分のお米が生産されているが、化石燃料購入費で800億円が流出している状態である。これを重大な問題と捉えている紫波町では、積極的な地域再エネ導入の取り組みがおこなわれている。地域の外にエネルギー代金を流出させなければ、地域は経済的に豊かになる。逆に流出させてしまうと、心も荒んでしまう。日本の脱炭素先行地域では50億円というお金を梃に脱炭素に取り組むことができるため、エネルギー代金流出防止の取り組みが期待される。
近年の日本ではフェイクニュースが多すぎるという話と関係があるが、日本は直近の10年間で最終電気消費量を12%ほど減らしている。これは住宅用太陽光発電の導入が進んだためである。データセンターが増えたり、さまざまな分野で電化が進んだりすることで消費量が増えると言われているが、減っているのが現状である。
日本のエネルギー消費量の内、建物が占める割合は約三分の一である。住宅での消費割合は「暖房」「給湯」「家電」が三分の一ずつを占めるが、断熱をすることで暖房は必要なくなり、お風呂も熱くしなくても済むようになる。断熱材をホットプレートの上に置きサーモグラフィーで見てみると、ほとんど熱を通さないことがわかる。断熱とは熱を断つことであるので、厚みが重要である。グラスウール(GW)の断熱材を屋根に20㎝、壁に10㎝入れると2025年の基準である等級4相当になる。また、住宅で最も熱が逃げやすいのは窓であり、等級4にするには窓をアルミサッシのペアガラスにする必要がある。等級4で約100kWh/m2程度のエネルギー消費量であり、今年の4月から新築において義務化された。また、同等の断熱材の厚みで、内側がプラスチックで外側がアルミサッシのアルミ樹脂複合の窓の場合は等級5となる。そして、樹脂サッシの窓にした場合は等級6となる。等級7は断熱材を屋根に30㎝、壁に20㎝入れたうえで樹脂サッシの窓にしなければならない。
国交省は等級4が2025年適合基準となったことを契機に、等級6と7を新たに設けた。等級5を2030年までに義務化する方向性となっているため、さらにその上に位置する等級6と7の将来的な義務化が議論されている。この世の中は「試しに一回やってみてうまくいったら、もっとやってみよう」というある意味で「調子に乗った社会」なので、私は調子に乗らせるのが一番良いと考えている。
5kWの太陽光パネルを載せ、断熱をしっかりおこない、昼に発電した余った電気でお湯を沸かし、EVを住宅につなげればエネルギー代金がかからない家ができる。エネルギー代金がかからないのは大きなメリットであり、価格が高くなっても購入する人は多い。また、追加で蓄電池を付ける人もいる。ペイバックタイムはおおよそ10年から15年程度だと思われる。
日本で地球温暖化の被害を最も受けているのは学校である。体育館には断熱材は入っておらず、エアコンも設置されていない。また、地域格差もあり、東京都では90%ほどエアコンが導入されているが、地方ではあまり導入されていないため、日本全体の導入率は18%ほどとなっている。教室もサーモグラフィーで見ると一目瞭然であるが、窓から熱が逃げている。学校の窓は床面積の5分の1にしなければならないという規則のため、とても大きい。これはかつて、電気を使わずに日射の光で教室を明るくすることを目的としていたためである。公立小中学校等の普通教室の99%では、平成30年の熱中症事故を受けて、空調(冷房)設備が設置されている。近年では「学校断熱のワークショップ」が開催され、グラスウールの断熱材を詰めたり、建具屋と協力して内窓をつくったりしている。このような取り組みは国交省の基準での評価は難しいが、確実に教室を暖かくすることができる。このワークショップは2025年グッドデザイン賞でグッドフォーカス賞[防災・復興デザイン]を受賞した。
より深刻なのは体育館である。例えば9月1日の東京のある体育館をサーモグラフィーで確認すると、断熱性能の低い金属の屋根が原因で、エアコンをつけていても効果があまりないことがわかる。800㎡の体育館の屋根の断熱を実施する場合、㎡当たり3万円ほどなので、合計で2400万円ほどかかる。高額ではあるが、ランニングコストは安くなるため、文科省も断熱を推奨しており、補助金を出している。しかし、それでもなお断熱と空調整備は高額なのが現状であり、多くが資金不足に悩んでいる。断熱費用が2400万円ほどで空調設備が2700万円ほどなので、合計5100万円ほどであり、二分の一を文科省が負担しても2550万円が必要である。
私はこの問題について、家庭用のエアコンを活用するのが良いのではないかと考えている。家庭用のエアコンは大量生産品なので低価格であり、性能としても十分である。2550万円ほどの負担は1500万円ほどまで抑えることが可能となるため、お金が無いのであれば実施すればよいと思うが、何か不都合なことが起こりうるのだろうか。家庭用エアコンを活用することはこれまでの慣習を破ることである。この答えは出ておらず、このリスクをどうとらえるのかを考えてほしい。
本報告の冒頭では、2050年までの脱炭素の実現可能性や脱炭素に取り組まなくてはいけない理由ついて参加者間で議論する時間が設けられた。また、報告後には、家庭用エアコンと業務用エアコンの性能やコストの違いに焦点をあてながら、報告者とフロアの間で議論がなされた。
「エネルギー転換の空間戦略-脱炭素化と地域の持続可能性の両立に向けて-」
小野寺弘晃(国立環境研究所 社会システム領域 地域計画研究室 研究員)
私の所属する国立環境研究所は環境省の外郭組織であり、廃棄物処理や生物多様性保全、気候変動対策などの幅広い分野の研究者が在籍する研究所である。社会システム領域は気候変動対策の社会実装を扱っており、私はその中にある地域計画研究室で地域エネルギー政策における気候変動対策や脱炭素化を研究している。私の専門分野は社会システム工学であり、エネルギーシステムを経済的側面から分析をする、狭義の意味でエネルギー経済学と呼ばれる分野である。
本日報告する「脱炭素化と地域の持続可能な発展を両立する将来像の仕組みとデザイン」についてであるが、トップダウンとボトムアップの二つアプローチがある。トップダウンのアプローチでは、各地域の特性を詳細に把握したうえで、日本全体で脱炭素化やエネルギー転換をしていけるのかを分析する。しかし、シミュレーションでの数値計算であるため、地域の実態を反映するのは難しく、限界がある。そこで、ボトムアップのアプローチをおこない、より地域に入り込み、地域の特性を詳細に考慮したエネルギー計画の策定支援をおこなっている。Webツールをいくつか作成しており、学生時代に作成した「地域エネルギー需給データベース」では各市区町村のエネルギー需給を可視化したりシミュレーションしたりすることができる。また、最近プロトタイプとして作成している「再エネ導入計画3D-WebGIS」では、再エネ導入時の景観や生物多様性への影響、気象条件に基づいた発電量などを3Dの地図上でシミュレーションすることができる。これらの2つのアプローチがあるが、私の業務に関係するのは主にトップダウンのアプローチであり、モデル研究や数式研究、シミュレーション研究をおこなっている。
一つ目のトピックは「再生可能エネルギー導入拡大の展望と課題」であり、全体を俯瞰し、モデリングやシュミレーションをする立場から検討する。気候変動対策においては排出量削減の目標達成が難しいという議論があるが、どのようにすれば目標を達成できるかを考えなければならない。今年の2月に地球温暖化対策計画が改訂され、現状から2050年まで直線的に削減し、2050年の排出量実質ゼロを目指すこととなった。気候変動対策は可能な限り将来世代に影響が出ないように2℃目標や1.5℃目標を目指しているが、1.5℃目標はぎりぎり達成が可能な範囲であり、その達成は都市や地域にかかっている。
脱炭素化にむけて再エネを大量導入することが重要であり、エネルギー基本計画では2040年の電源構成における再エネ比率を4割から5割にするという目標が定められている。これをギガワット(GW)ベースにして考えると、太陽光で約170GWから230GWであり、風力では約18GWから39GWである。IPCCのAR6シナリオ群の日本の165のシナリオを確認すると、太陽光に関しては基本計画の目標と同じであり、2040年で約200GWとなっている。しかし、風力に関しては2050年で200GWとなっており、計画とかなり乖離がある。基本計画の目標は現実的な数値であるが、脱炭素化を本気で目指すならば、より野心的な取り組みが必要である。
IRENAの2020年から2024年の風力発電の累積導入量に関するデータを確認すると、2024年には欧州で約250GW、米国で約150GW導入されている。これらに比べると、日本の導入量である6GWは見劣るように見えるが、導入量は確実に増えている。AR6のシナリオを確認しても現状で6GW程度なのは想定内であり、2030年から2040年と2040年から2050年の飛躍的な導入を実現できるかどうかが重要である。
また、太陽光に関する累積導入量のデータを確認すると、欧州で約350GW、米国で約180GW導入されており、日本は100GWに届きそうな状況である。しかし、他国が指数関数的に導入量を増やしている一方で、日本の導入推移は対数関数的で緩やかであることがわかる。この日本の導入推移は、政策誘導のあり方を考えると至極当然である。FIT買取価格は制度開始時の2012年で約40円/kWhであり、発電原価は十数円であったため、太陽光発電による儲けは大きかった。しかし、近年では発電原価があまり変わらずにFIT買取価格が10円を下回っており、事業性が下がっているため、導入量が減っているのである。
太陽光パネルを200GW導入した社会を想像するのは専門家でも困難である。また、エネルギーの専門家はGWという単位ばかりを用いて議論をする傾向にあるが、それでは理解をするのが難しい。そのため、私は2023年末時点の計画値を含むデータを活用し、地図上で導入量の可視化をおこなった。可視化においては市区町村内に太陽光は黄色い点、洋上風力は青い点で、それぞれ導入量に応じた大きさの点を代表の座標に示した。
また、最近では脱炭素化した場合の可視化もおこなった。需要が多い場所で多く導入するのが経済合理的であり、関東に注目すると、可能な限りの屋根と土地に太陽光が導入されることがわかる。洋上風力は80GWまで導入が必要と試算されるが、茨城沖や千葉沖で見渡す限りの風車が導入されることがわかる。なお、このシナリオは再エネ100%ではなく約70%であり、既存のガス火力や原子力も可能な限り使うシナリオである。また、このシミュレーション結果は理論的・技術的に実現可能であるが、現実的・社会的に実現可能かは不明である。私はこの点に興味を持って研究に取り組んでいる。
なぜ技術的な実現可能性と社会的な実現可能性の間にギャップがあるのかというと、再エネには潜在的な障壁が多いためである。例えば、気象条件や景観への影響、災害リスク、生物多様性の影響などは想像しやすい。また、社会的受容性も非常に大きな問題として顕在化している。そのほかの点では、技術者不足やサプライチェーンリスク、ガバナンスの欠如などが挙げられるが、これらを除けばほとんどの障壁が適切な立地によって解決できると考えられる。つまり、地域社会・エネルギーと調和する再エネ導入拡大のために、空間的戦略が重要となる。
そこで出てくるのが、次のトピックである「高解像度のエネルギーシステムモデル」である。エネルギーシステムとはエネルギーの需要と供給の構造である。どのような資源をどのようなエネルギーキャリアに変換して、どのような需要家が使っているのかという全体の構造を数理モデルとして落とし込み、最もコストが安くなるように各地が設備を配備、維持管理する最適化モデルを構築した。このモデルにより、2020年から2050年までの発電量やコスト、CO2排出量の推移を算出し、2050年にどのような電源の分布になっているのかやそれぞれの電源がどのような役割を担っているのかを示すことができる。そして、このモデルを活用することで、脱炭素電源の導入・立地戦略の検討が可能になり、また、地域レベルの気候変動緩和シナリオの作成が可能となるほか、さまざまな分析が可能とる。なお、このモデルは全国の1741市区町村に対応する空間解像度を有し、空間解像度に関しては世界最高のモデルだと思われる。
最近ではこのモデルを活用し、環境研究総合推進費1MF-2502において多様な技術と社会像を考慮した複線的脱炭素シナリオ分析に取り組んでいる。例えば、既存の電源を活用・増強して脱炭素の実現を目指すという考えがある一方で、風力・太陽光を積極的に活用して脱炭素を目指すという考え方もあり、両方の立場からシナリオを作り、再エネ分布の分析している。両シナリオともコストが全く同じであり、社会的な負担は変わらないが、既存の電源を活用する方針の方が技術的な不確実性のレベルが高い。一方で、積極的に導入を進める方針の場合は社会的な不確実性が高い。また、いずれの方針でも日本で脱炭素化をするには洋上風力が重要になることがわかる。
続いてのトピックは「生物多様性保全と脱炭素化の両立に向けた再エネ導入戦略」である。近年、生物多様性については、カーボンニュートラルと同じような土俵にあるとみなされている。気候変動対策の目標はカーボンニュートラル・Net Zeroであり、その背景には気候変動枠組み条約があり、パリ協定の中で2℃目標や1.5℃目標が示されている。また、IPCCが科学的エビデンスに基づいて政策に影響を与えている。生物多様性に関しても生物多様性条約や昆明・モントリオール生物多様性枠組みというものがあり、IPCCと同じような役割を担うIPBESという組織が存在する。また、カーボンニュートラルに対応する「ネイチャーポジティブ」という目標があり、これは失われつつある生物種・生物多様性を逆転させ、増やしていくという目標である。そして、「30 by 30」というのが、Net Zeroに対応するのもであり、土地や海域の30%を2030年までに保全する目標である。
どちらもグローバルな目標として重要であるが、カーボンニュートラルを実現するために再エネを導入していくと、生物多様性に影響を及ぼす恐れがある。一方で、ネイチャーポジティブを実現するために土地利用規制を進めていくと、再エネの適地が減少し、脱炭素化の実現に対する脅威・費用の増大が懸念される。そこで、この二つの両立が可能であるかを検討するため、分析をおこなった。環境省のREPOSに準拠して太陽光の設備容量を示したが、国立公園や自然環境保全地区、鳥獣保護区などすでに法的に保護されている地域に加え、非常に強い生物多様性保全の規制を設けた場合、導入ポテンシャルはかなり減ることがわかった。風力に関しても陸域と東日本側の海域でポテンシャルがあまり残らないことがわかった。ただし、この結果は極端な結果である点に留意する必要がある。
先ほどのモデルを用いて、保全すべき土地には再エネ設備を設置せずに脱炭素化を達成できるのかを検討すると、技術的には答えを出すことができる。生物多様性保全を現状維持し、安価な電源を求める場合には生物多様性上のリスクが高い地区にも導入が進む可能性がある。これは鳥の飛翔経路については導入が除外されないためである。実際の事業ではアセスメントが実施されるため、導入されるとは考えられないが、現状のREPOSの想定だけで考えると理論的には開発可能なエリアとしてみなされてしまうのである。一方で、徹底して土地を保全する場合は、電源の分布に若干の違いが見受けられる。一番大きい変化は太陽光の分布であり、現状維持の場合は需要家にできるだけ近い地域に導入されるが、徹底して土地を保全する場合は適地が限られるため分散する。また、福島沖や茨城沖、千葉沖の海鳥のホットスポットとなっている場所では導入されず、理論上で生物多様性保全の観点でリスクが低い中国地方の日本海沖で導入が進むという結果になる。そして、土地利用規制強化により再エネ導入分布が変化することで、電力コスト(電力原価)は大幅に増加する可能性がある。このコストを社会が受けられるかどうかが重要な論点となる。
続いてのトピックもトレードオフについてであり、「脱炭素化とデジタル化のトレードオフを緩和する電力システムの空間戦略」である。ここでのデジタル化の話題に関して端的に言うと、データセンターが増えると脱炭素化が難しくなるということである。脱炭素化を進めると短期的には電力価格が上昇し、デジタル産業の収益性に対する脅威となり、デジタルサービスユーザーへの価格転嫁も起こりうる。AR6の価格シナリオを確認すると、現状維持で2100年時点で平均気温が4℃上昇するシナリオでは電力価格の変化は小さい。一方で、1.5度に抑えようとすると、移行期間に当たる2030年頃に電力価格がスパイクする可能性が高いことが示されている。電力会社がこの費用を負担をする可能性もあるが、基本的には消費者へ転嫁されると考えられる。そして、デジタル化を進めると、電力需要が増え、短期的には火力発電の焚き増しによってCO2排出量が増大し、長期的には脱炭素電源へのさらなる投資が必要になるため脱炭素化の実現が脅かされることになる。このトレードオフについては政府やメディアも取り上げることがあるが、エビデンスはほとんどない。そのため、エビデンスに基づいてこのトレードオフについて取り扱うのは日本では私の研究が初めてだと思われる。
データセンターの何が問題かというと、東京や大阪などで局所的にGWスケールで需要が増加させることである。現状の面積ベースで確認するとデータベースの約90%が東京と大阪に集積している。これには通信の遅延の最小化という目的があるが、昨今では光電融合技術などの登場によりこの制約は緩和されつつある。総務省が取り組むデジタルインフラ整備計画2030からもわかるように、近年ではデータセンターを分散させる取り組みがなされている。
データセンターを増やすと送電線を増強したり、蓄電池を増やしたり、火力発電を焚き増したり、再エネを増やしたりする必要があり、追加的費用が掛かる。そこで、各地域にデータセンターを配置した場合、どれほどの追加的費用がかかるのかを分析した。東京周辺の需要が密集している地域にさらに需要を足すと、需給のバランスの関係で追加的費用が高くなる。一方で、東北地方や北海道などの脱炭素電源のポテンシャルに対して需要が少ない地域では追加コストが低くなる。このような地域では結果的にデータセンターが支払う費用が安くなり、需要家にとっても電力システム側にとっても好都合となる。具体的に確認すると、データセンターが集中する印西市では7.7円/kWhの追加コストがかかるが、石狩市では6.2円/kWhとなり、潜在的には約20%電力コストを削減できることがわかる。
また、実際に最適となる配置を計算することが可能であり、例えば、災害リスク・インフラアクセス・都市計画に基づくデータセンター立地ポテンシャルを考慮し、データセンターと電力システムの両方にとって電力コストが最小となる立地を求めた場合、やはり東北地方や北海道に分散して立地した方が良いことが示される。データセンターの拡大と脱炭素化を同時に進めようとすると、電力コストは相乗的に上昇してしまう。しかし、データセンターを分散させることでその上昇を緩和することができるのである。
データセンターを引き付ける誘因になっているのは、どれだけ再エネ資源があるかである。東京でデータセンターを拡大しようとすると再エネが追い付かないため、ガス火力を延命させ、排出したCO2をCCSで地下に埋めるという技術的不確実性が高いことに取り組まなければ脱炭素化が達成できなくなる。データセンターが分散すれば、地方の再エネを活用することができ、ガス火力やCCSを減らし、特に洋上風力といった再エネが増えていくことになる。
最後のトピックは「脱炭素化と地域の持続可能性の両立に向けて」である。これは私が主に修士課程の時に取り組んだトピックであり、2021年に『エネルギー・資源学会論文誌』に投稿した。この研究では、脱炭素社会における地域の持続可能性に関する考え方として、再生可能エネルギーを縦軸に、地域資本(人的資本、自然資本、文化資本、経済的資本…)を横軸に設定し、どちらも満たされている地域は気候変動緩和と経済的自立の観点から持続可能性に貢献しているということを図示した。
実際に多くの地域がどのように分布しているのかを確認すると、どちらも満たされている地域は特殊な地域であり、数が少ないことが確認された。横軸となる地域資本は計測するのが難しいが、地域の活力を測る財政力指数というものを代替指標として活用した。また、縦軸は再エネ導入ポテンシャル-エネルギー需要(TJ/年)とし、プラスになっている場合、需要より再エネが多く、マイナスの場合は需要が再エネを上回っている状態である。財政的に余力があり、再エネも非常に豊富にある地域は単独で脱炭素・気候変動対策を推進することができ、経済的自立にもつながっている地域であるが、このような地域は1741地域の内223地域しかないことが示された。過半数の地域は、再エネが需要を上回っているが、財政的な余力がない地域であった。また、財政的に余裕があり、再エネより需要の方が大きい地域には市が多いことが示された。この研究からは、多くの地域では資源・財政のどちらか、または両方が不足するため、地域単独での脱炭素化には限界があるということがわかった。また、特徴の異なる地域同士が連携することで、個別地域の課題を解決できる可能性があることがわかった。実際に、現在の脱炭素先行地域でも複数の地域による共同提案が見受けられる。
本日の報告内容をまとめの一点目は、脱炭素化のための選択肢は多様で広範であるということである。もちろん再エネ100%というのも一つの選択肢であるが、CCSのように炭素を回収する技術に頼るのも不確実性は高いが一つの選択肢である。様々な選択肢を探求し、技術的に実現可能かつ社会的に受容可能な脱炭素化への道筋を明らかにしていくことに取り組んでいく。まとめの二点目は、再エネが社会にもたらす変化を、より深く理解する必要があるということである。本日は地図上で分布を可視化することで、どのような絵姿になるのかをイメージしやすくしたが、正負両面を有する外部経済性を明らかにすることが重要となる。極論を言うと、これをすべて明らかにすることで、脱炭素化と地域の持続可能性を両立する将来像を描くことが可能となる。まとめの最後の点は、地域・分野を越えて全体を俯瞰し、統合的に取り組むことが重要であるということである。脱炭素化を達成しようとするとき、電力セクターだけで達成するのは難しく、燃料セクターやデジタルセクター、生態セクターなどとのカップリングが重要となる。個別のセクターだけで最適化をしようとすると、外部性を見逃すこととなる。地域に関しても同様であり、地域間の連携が重要である。地域間・セクター間の連携は、脱炭素化や生物多様性保全、デジタル化といった様々な目標と地域のビジョンの同時達成には不可欠である。
報告後は土地利用規制緩和による生態系サービス損失と補償についてや、風力と太陽光の導入バランス、既存のガス火力や原子力、石油精製設備に対する生物多様性への考慮など、モデルに関する議論がなされた。また、報告者が手掛ける「再エネ導入計画3D-WebGIS」のプロトタイプの紹介とそれに関する質疑応答がなされた。