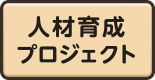2025年 7月18日(金)研究会 議事録
第3回研究会
2025年7月18日 15:00‐18:00
於:京大吉田キャンパス本部構内「法経東館」地下 1 階 三井住友銀行ホール
登壇者:安田陽(ストラスクライド大学 アカデミックビジター、九州大学 洋上風力研究教育センター 客員教授 、環境エネルギー政策研究所 主任研究員)
尾形清一(京都大学大学院 エネルギー科学研究科 准教授)
第3回研究会では前半に、ストラスクライド大学で研究に取り組む安田陽先生より、英国の脱炭素・再エネ政策について陸上風力を中心に報告がなされた。後半には、京都大学大学院エネルギー科学研究科の尾形清一先生より、現在力を入れている東南アジアの再エネ研究の紹介に加えて、営農型太陽光発電について日本の課題を中心に報告がなされた。
「英国の脱炭素・再エネ政策~陸上風力の動向を中心に~」
安田陽(ストラスクライド大学 アカデミックビジター、九州大学 洋上風力研究教育センター 客員教授 、環境エネルギー政策研究所 主任研究員)
1.統計データに見る日英比較
本日は私の研究拠点である英国の脱炭素・再エネ政策について報告する。英国は洋上風力の取り組みが有名であるが、ほとんどの情報は日本語でも入手可能である。そのため本日は、日本にはあまり情報が入ってこない英国の陸上風力について報告する。
日本政府はしばしば英国の政策を参考にしているが、肝心なところは伝わっていないという印象を受ける。まず、CO₂削減目標の日英比較についてであるが、日本については国際的な基準の1990年比ではなく2013年比での削減目標を設定しており野心的な目標設定とは言えない状態である。また、日本の削減目標を年推移で表すグラフで見ると削減目標は直線的であり、野心的であるとは言えない。一方で英国の削減目標は1990年比である。また、排出量に着目すると1990年代より真面目に取り組んでおり、2010年代には大幅な削減に成功している。そして、旧政権と新政権の削減目標を比較すると、あまり変わっていないという解釈をすることも可能だが、政権交代に影響されずやるべきことをしっかりやっている国とも捉えることができる。もちろん、英国国内では現状の目標では全然削減量が足りないという議論もなされている。
続いて、再エネの将来目標の日英比較についてだが、さまざまな国際機関の科学的な報告書を確認すると、どの報告書も再エネの導入が最も低コストでかつ大量のCO₂を削減できるとしている。このような科学的な知見を背景に各国は再エネの導入を進めている状態である。IEA(International Energy Agency)のシナリオでは2050年には再エネ導入率は9割になるとしており、このシナリオは国際標準となっている。この話を大学生にすると、「知らなかった」という声をよく耳にする。これに関しては学生の勉強不足というよりも、このことを政府もメディアも情報を流さない国の状態が原因であると考えられる。私の『2050年再エネ9割の未来 脱炭素達成のシナリオと科学的根拠』(2025年、山と渓谷社)では、このように情報が流れてこない状態を「ふんわり情報統制」ということばで表現している。
英国の再エネ導入量目標は2030年に8割となっており、このことを日本の人に伝えると荒唐無稽だという意見が出てくる。しかし、コロナで停滞していた時期があったものの2010年代からの導入率の上昇を考えれば、荒唐無稽な目標ではないことがわかる。また、導入目標に関しても削減目標と同じように、政権交代の影響を受けていない。2024年の総選挙の時には、日本のニュースでは気候変動は選挙の争点になっていないという報道のなされ方がしていた。しかし、これは気候変動を否定しているリフォームUKを除いてすべての政党がそれなりに高い目標を掲げているために争点になっていないという状況であり、現在の日本の参議院選挙で争点になっていないのとは全く違う状況である。
また、去年に私が英国の多数の再エネ関係者に対して行った2030年の目標に関するインタビューでは興味深いことが明らかになった。8割導入という目標に対して「無理ではないか」「難しい」といった回答が多く、それに対して何割なら可能かという質問をすると70%~75%なら可能という回答が多かった。英国では8割という高いバックキャスティングによる目標を掲げることによって、たとえ結果としてオフトラックになってもIEAの目標を上回るのが前提となっている。オントラックであることが良いとされ、世界的にみて低い目標を掲げている日本とは大きな違いである。国連や国際機関は理想論や科学的な最適解を目標に掲げ、英国・欧州はそれを上回る目標設定をしている。一方で日本はフォワードキャスティング、つまりは「現実的」であり、理想論を嘲笑している状態である。この状態は再エネにかかわらず、人権問題や外国人排斥の問題でも同様であり、日本は先進国ではなくなりつつあると捉えることができる。
私は昨年、学術誌『Renewable and Sustainable Energy Reviews』にてC-Rマップを用いて石炭と再エネの相関関係を可視化した。30年前の英国は大量の石炭を使い、再エネはほとんどなかったが、30年間かけて再エネを伸ばし、石炭火力の割合をほとんどゼロまで縮小させたことがマップからは読み取れる。2024年10月に石炭火力は廃止されたため、今新たにマップをつくるなら石炭の割合は完全にゼロとなる。また、このマップからも旧政権が再エネの導入に力を入れていたことが読み取れる。一方、日本のマップをみると迷走している軌道を描いており、むしろ石炭の割合を増やしていることが読み取れる。原発を止めたから石炭火力を増やさざるを得なかったと主張する人が多くいるが、このマップをみると原発を止める前から虎視眈々と石炭を増やしていたことがわかる。ようやく石炭の割合が減りだしたのが2015年であり、むしろ原発が止まっているときの方が減っている。また、FITが始まり再エネがたくさん導入されたという風潮であるが、欧州の他の先進国と比べるとまったく足りていない状態である。OECDの37か国についても比較したが、日本と韓国だけが石炭を減らし再エネを増やすという潮流から外れている状態である。
英国を構成する国別に再エネ導入量の推移を確認すると、スコットランドは100%を超えている状態であることがわかる。つまり、自国での消費電力量以上に再エネで発電し、それを隣国、主にイングランドに輸出している状態である。ウェールズについても英国全体の再エネ導入割合を超えている状態である。日本ではいまだに再エネ100%は荒唐無稽だと考えられる傾向にあるが、実際に100%を達成している国はあり、スコットランドのように数年後には200%になるような国も存在している。日本全体で不可能だとしても北海道や東北では可能性があり、このことについては単なるエネルギー政策だけでなく地方分権のあり方も含めて考える必要がある。
続いて、スコットランドとイギリスの再エネ設備導入量(kW)について比較する。イングランドは過去10年で着々と洋上風力を増やしており、このことは日本でも報道を通じて情報が入ってきている。また、日本にはあまり情報は入ってこないが、太陽光についてもイングランドでは年々増加している。スコットランドについては、洋上風力が有名という話をしばしば聞くが、それは直近5年程度の話である。スコットランドが地道に伸ばしているのは実は陸上風力であるということがデータで示されている。単年度の導入量に着目するとイングランドは2015年に太陽光の導入を急速に増やし、そこから下がっていることがわかるが、これはCfD(Contracts for Difference)導入のためであり、日本のFIT導入の時に近い状況である。また、イングランドでは陸上風力の導入が減っていき、現在では事実上ゼロであるが、これはウィンドバンと呼ばれる事実上の風力禁止令が出ているためである。しかし、同じ英国内でもスコットランドではウィンドバンは適用されていないため、コロナで停滞した時期を除いて毎年着実に陸上風力を増やしてきたことがわかる。近年になってようやく洋上風力の導入も増えているが、このことについては、陸上風力に注力しているため洋上風力を導入しなくても問題ないためとも解釈することができる。
日本の設備導入量について着目すると、太陽光ばかり導入され、風力はあまり導入されていないことが明白だが、この状態はイングランドのウィンドバンの状況と非常に似ていると捉えることができる。スコットランドの系統規模(年間消費電力量)は北海道の3分の2程度、そして日本の50分の1程度である。それにもかかわらず、スコットランドは過去10年平均で日本の2倍程度の風力を導入している。私はこのことから、「日本は狭い島国だから風力は入らない」という見解に違和感を感じており、日本になかなか風力発電が導入されないのは自然環境や電力系統の問題でなく、単に政策の問題であるという仮説を立てている。
2.政権交代後の英国の脱炭素・再エネ政策
次に、各報告書を確認しながら政権交代後の英国の脱炭素・再エネ政策がどのような変遷をたどったのかを確認する。英国では2024年7月の総選挙で労働党の圧勝による政権交代があったが、それまでの保守党政権が何もしていなかったわけではなく、政権交代以前の取り組みも継承されている状態である。
政府の報告書の前に、政府の助言機関である気候変動委員会(CCC:Climate Change Committee)の報告書を確認する。この委員会は2008年の気候変動法(Climate Change Act)により、英国特有の組織分類である「非政府公共組織(NDPB:non-departmental public body)」のひとつとして設立された。NDPBは政府の組織からほぼ独立して業務を遂行し、議会を通じて国民に説明責任を負っている政府省庁に属さない非政府組織である。例えば、日本でも有名な英国放送協会(BBC)もNDPBに該当する。CCCの目的はホームページに記載があるが、排出目標について英国政府および英国内各国政府に助言をし、温室効果ガスの排出削減、気候変動の影響への備えと適応の進捗状況を議会に報告することである。人事については科学者から選出され、公平性や透明性の観点から気候変動に関して政府に助言をしている。CCCの報告書内ではCB(carbon budgets)について計算がなされており、2050年までの炭素排出削減の道筋について助言がなされている。CBはCOPやIPCCでも盛んに言及されているが、日本ではほとんど無視されている状態である。CCCの報告書内ではCBという用語は162回も使われている。
英国政府が2024年12月に出した報告書『Accelerating to Net Zero』を確認すると、CCCの報告書の助言がそのまま採用されていることがわかる。そして、この報告書の副題は「CCCへの回答」となっており、助言機関からの提言を政府が回答したということを示している。報告書の内容は中立的な科学的知見に基づいたものであり、労働党政権の新規性があるわけではない。しかし、政治的な利害関係でなく、科学的知見に従うというのは労働党政権の新規性だと捉えることができる。
この政府の報告書の中で取り組みとして述べられていることは、先ほども言及したように保守党政権の時とあまり変わっていない。しかし、その中でも新たな点はウィンドバンの撤廃である。先ほどお話ししたようにイングランドのみ風力の導入が止まった時期があったが、労働党は選挙時にもそれを撤廃することを掲げていた。また、CCCはウィンドバンについては保守党政権の時から廃止を助言していた。
保守党政権の時のウィンドバンについてはさまざまな団体が声明を出していた。比較的独立的かつ再エネ推進指向の団体のものを確認すると、そもそもウィンドバンとはなにかというのを説明している(※1)。それによると、国家計画政策枠組み(NPPF)という日本のエネルギー基本計画に近いもののなかで、「提案が地域コミュニティの支持を得た場合にのみ、陸上風力発電の提案を受け入れることができる」という文が記載されており、これがイングランドで忠実に解釈され、たった一人でもプロジェクトに反対する人がいれば、そのプロジェクトは白紙になるという状態が2015年頃から続いていたのである。また、これが「陸上風力発電の提案に対して、他の再生エネルギープロジェクトよりも高い障壁を設定し、効果的なモラトリアムとして機能することになった。」という皮肉な説明がなされている。また、この団体によると、2014年から2024年で54件の陸上風力発電の計画申請が即座に却下または撤回されており、また、この政策の影響は再生可能エネルギー発電以外にも及んでおり、9億ポンドの経済生産が犠牲になったとしている(※2)。
新政権は選挙で勝った3日後にはウィンドバン廃止の声明を出しているが、この情報も日本にはほとんど流れてきていない。政府は廃止を政府からの強いシグナルと表明しつつも、計画申請は依然として通常の方法で制度を通過する必要があるため、陸上風力発電所の無秩序な建設ラッシュにはならないとした。また、エネルギー安全保障を支え、気候変動に対処する開発に対して、計画制度が事実上の障壁として機能するのを防ぐことを目的とし、これらはすべて、既存のシステムを首尾一貫して戦略的に機能させたいという願望を示しており、これは多くの人にとって安心材料となるとした。
続いて、英国の電力事情に焦点を移す。欧州の文脈で英国の発送電分離について考えると、英国はカオスな状態であった。なぜかというと、一般的にはEU Directive 09やEU Directive 2009によって欧州での所有権分離が進んだとされるが、英国は例外であった。英国はブレグジット前からEU Directive違反すれすれのことをしており、2019年にようやくNational Grid Electricity System Operator (ESO)を設立したものの、EU Directive 2009から10年も経った後である。この時点でようやくNational Grid Electricity Transmission (NGET) からESOが法的に分離されたのである。スコットランド内ではさらに複雑な状態であり、ScottishPowerとSSEN (Scottish & South Power Network) Transmissionというスコットランドの2大電力会社が送電網を所有し、ESOに運用権だけを渡している状態であった。つまり、法的分離とアメリカ型の機能分離の折半のような状態であった。紆余曲折の後、2024年10月にはNESO (National Energy System Operator) が設立されたが、ESOからNESOに名前が変わっただけで、実態はあまり変わっていない。NESOは独立系統運用計画者 (ISOP) としてグレートブリテン島の系統運用・計画を担う (機能分離)。しかし、NGETやScottishPower、SSEN Transmissionが引き続き送電網を所有している。ようやく英国にてアメリカ型のISOが完成したことになるが、これに関して英国はあまりよくない例であると言わざるを得ない。
政権交代後、2024年11月にNESOは『Clean Power 2030』という報告書を出した。この報告書では2030年の電力ネットワークのシミュレーションを行っているが、再エネが8割を占める結果となった。NESOは日本でいう東京電力パワーグリッドや広域機関のような組織であるが、そのような組織があと5年で再エネを8割にすると言っているのは、日本にとっては衝撃的な内容である。しかし、このような情報も日本には全く入っていない。
NESOは再エネの専門組織ではなく、送電線の専門組織である。そのNESOはガス火力は2030年も依然として電力の安定供給のために必要だとしているが、その割合は5%未満としている。日本の場合、再エネは不安定であり、2040年も火力は4割残さないといけない、という主張がなされている。日本と英国は同じ狭い島国であるが、ユーラシア大陸の西と東で大きな違いである。このような情報も日本語にはされておらず、意地でも日本語にしたくないという状況のように感じている。
NESOは安定供給のために35GW程度のガス火力を待機させなければならないともしている。ただし、待機させるとしても2030年代前半までとしている。ここに関しても、送電線の専門組織が言及しているということは注目に値する。
日本の方によく、なぜそのようなことが英国では可能なのかと聞かれる。その時にするのが「系統柔軟性(flexibility)」の話であるが、ガス火力以外にも調整(ディスパッチ)可能電源は豊富にある。日本において、ディスパッチ可能な電源についてはアンモニア発電や水素発電の話になりがちであるが、バイオマスもこれに該当する。NESOは火力の代わりとしてのバイオマスの必要性を強調している。当然バイオマスのほかにもCCSや水素プロジェクトにも取り組むとしている。さまざまな柔軟性をかき集めることが重要であり、このような考え方が日本には必要である。調整力は火力や蓄電池だけでなく豊富にあるため、それらの手段を可能な限り使うことが重要である。
柔軟性はどこから生まれてくるのかというと、供給側からだけでなく需要側からも生み出すことができる。例えばSmart chargingやVehicle to Grid (V2G)などがある。また、I&C Demand Side Response (DSR)は日本の文脈ではデータセンターが含まれる。データセンターがたくさん入ると原発が必要という主張があるが、データセンターは基本的にはフレキシブルな運用がなされている。AIの学習はいつでもやっているわけではなく、電力が高くなった時にわざわざ学習をしない。学習が止まればデマンドレスポンスが効き、むしろインカムさえ出てくる状況であるが、このような発想は日本には全くなく、データセンターがあたかもベースロード運転するかのような議論しかない状態である。
以上のような電源構成のシミュレーションはNESOの本来の仕事ではない。NESOは送電線の将来を考えるために、その前提条件として将来の電源構成をシミュレーションしたのである。シミュレーションの結果を踏まえつつ、英国が南北に細く、送電線もこれ以上はあまり立てられないことを考慮し、洋上ケーブルをどんどんつくるべきだという報告をしている。日本でも広域機関により取り組まれているが、CBAをかけて出てきたのは北海道から柏崎にかけての1ルートだけである。これはなぜかという質問がよくなされるが、再エネ目標があまりにも低いため、CBAをかけても便益が出ないためである。再エネがたくさん入って、電源構成が変わっていくからこそ送電線の便益が生まれる。再エネの割合が低いことにより、電力業界への投資が増えず、雇用も生まれないのである。英国、欧州の状況をみることで、このようなネガティブスパイラルが起こっている日本の状態の解釈が可能になる。
続いて、2024年12月に発表された英国政府による電源に関する報告書を確認する。何度も言うが、これも全く日本語になっていない。シナリオをみると再エネ約8割、火力約5%となっており、NESOのシナリオとほとんど同じである。労働党政権は一貫して科学者の言うことを聞くことを徹底している。
本日は再エネを中心とした報告だが、参考として多くの人が気になっている原子力についても報告する。日本では、英国は原子力を推進しているという報道がなされているが、政府の報告書内ではHinkley Point以外の原発新設は言及されていない。また、日本が好きなSMR(Small Modular Reactor)やRAB(Regulatory Asset Base)モデルへの言及も一切無い。昨年7月以降で新政権がRABモデルに関して言及しているドキュメントはインターネット上を探しても見つからない。旧政権がRABモデルをやると言ってしまったため、やめるとは簡単に言わないとは思うが、新政権はSMRやRABモデルに全く興味がない状態である。英国は原子力を減らすと明言しているにもかかわらず、そのことは日本ではなぜか報道されず、英国は原発を推進しているという報道ばかりがなされている状態である。
政府の報告書はCCCやNESOの報告書と同じような内容であり、新政権の独自性を探すのは難しい。しかし、国民向けにわかりやすい説明をしている点は注目に値する。例えば、CO2排出量や再エネ導入の現状や目標を車のスピードメーターのような図を用いて表している。また、需要側の柔軟性や連系線、ディスパッチ可能な電源、長期電力貯蔵に関しても同様の図でわかりやすく説明がなされている。
そして、そもそも何のためにネットゼロを目指すのかについても、報告書の最初に説明がなされている。ここでもわかりやすくイラストを記載し、エネルギー安全保障や健康、雇用、貧困対策、食料安全保障対策との関連を説明している。
3.スコットランド陸上風力の取り組み
スコットランドの洋上風力についてだが、この報告については今までのようなエビデンスベースの定量的分析ではなく、私のヒアリングや個人的な経験に基づいている。そのため、学術研究としては未完成であるが、現地の研究者として参考までに紹介する。
イングランドではウィンドバンがあったのにスコットランドではなかったことについてスコットランドでさまざまな人にヒアリングをしたが、再エネ産業団体の「我々は普通のことを普通にやってきただけ。イングランドがオウンゴールしたに過ぎない。」という回答が印象的であった。また、他の人たちからの回答も同じような内容であった。この「普通のこと」をするためにスコットランドではどのような努力がなされているのかを明らかにするのが私の今後の調査研究課題である。スコットランドは北海道ととても似ており、系統はとても脆弱で、系統制約に関しては北海道よりも厳しいが、再エネが大量導入されている。また、スコットランド人、イングランド人は厳しい自然保護や景観保護を実施している。これらを普通のこととして実施できる要因を調べていきたいと考えている。
スコットランドの事例としてScottish Power Renewables(SPR)が所有・運営するWhitelee風力発電所について説明する。ここは風車基数が215基、総容量は539 MWとなっており、英国最大の風力発電所であり、原発とは比較したくないが原発の約半分程度の容量である。また、スコットランド最大の都市であるグラスゴーから車で30分ほどの位置に立地しており、グラスゴーからも見える状態である。これについては私の印象だが、ネガティブな印象はほとんどない。私はさまざまな国に国際会議のために滞在しているが、たった1週間の滞在でも風力反対を表すポスターを目にする。スコットランドには1年以上滞在しているが、そのようなポスターは一度も目にしたことがない。英国ではパブやタクシーの人たちも気候変動や再エネの話をするが、そのような人たちから意見を聞いても反対の意見は聞いたことがない。そして、発電所内のトレイルルートは24時間365日開放されている。英国ではpublich pathというものがあり、私有地でもpathを通る権利はあり、それはここでも徹底されている。
Whitelee 風力発電所は運転から10年経過し、2019年には経済分析の報告書を出している。その中ではCAPEXやOPEXにおいてスコットランドにお金が落ちていることが示されている。損益分析においてはコストがスコットランド内に落ちることで、雇用が生まれ、直接的、間接的に利益が出ていることが示されている。
さらに興味深いのはRSPB (Royal Society for the Protection of Birds, 王立野鳥保護の会) のバッジが発電所内で販売されていることである。これはWhitelee 風力発電所がRSPBから表彰されたためであり、このことはSPR社が開発当初から王立野鳥保護の会スコットランド支部やスコットランド自然遺産協会、スコットランド森林土地協会などの自然保護団体に相談し、ワーキンググループを結成したことに由来している。その主な目的は、単にプロジェクトの影響を最小化するのではなく、生態学的生息地を強化し、環境遺産を創出することである。ワーキンググループは、ブラックグースのような在来種や、さまざまな高地の野生生物のための環境改善に取り組んできた。再エネ事業は自然環境団体とのトラブルが起きがちだが、しっかりと協力関係を築くことができれば、トラブルを避けることができるのである。
Whitelee 風力発電所はグラスゴー科学博物館とも連携しており、発電所ツアーやワークショップなどが実施されている。発電所が市に溶け込んでおり、市民・学生の科学教育の一環として活用されているのである。日本では風力と言えば低周波やバードストライクというイメージを持つ人が多いが、このようにしっかりと取り組んでいる事例はある。
4.まとめと日本への示唆
最後に、日本と英国のネットゼロ関係の文書・報告書を確認し、それぞれの中で特定のキーワードがどの程度出てきたのかをカウントした結果について報告する。私は結果をグラフ化してみたが、これをみると英国では「カーボンバジェット」「便益」「健康」「貧困」などの幅広いキーワードが何度も出てくるのに対し、日本ではあまり出てこないことがわかる。また、日本では「陸上風力」についてもほとんど言及されていないことがわかる。裏を返せば、これらのキーワードにしっかりと言及すれば日本も軌道修正できるのではないかと思う。
必ずしも英国ではすべてが順調に進んでいるわけではない。例えば、断熱や鉄道に関しては英国はまだまだ改善が必要であり、英国よりも日本の方が優れている分野もある。しかし、エネルギーと電力に関していえば、英国は系統運用の専門組織が5%のガス火力で問題ないと言っているのに対し、日本は2040年でも40%必要だと言っているのを考えれば、大きな差があると言わざるを得ない。今回取り上げたような、日本ではまだ議論されていない観点について今後は議論をしていく必要があると思う。
報告後は英国やヨーロッパの再エネ導入に関して質問がなされたほか、なぜCCCのような忖度のない報告が可能なのかや、近年リフォームUKが議席数を伸ばしていることなどについてディスカッションがなされた。
※1 Charlie Reid: Ban on Onshore Wind in England is Lifted, Ashrust, 09 July 2024
https://www.turley.co.uk/news/economic-cost-decade-onshore-wind-ban
※2 Nicola Riley and Chris Pickup: Decade of blocked onshore wind farms cost £900 million in economic output, Turley, 15 April 2025
https://www.turley.co.uk/news/economic-cost-decade-onshore-wind-ban
再エネ政策を考えるための分離融合研究(総合知)に向けて
―営農型太陽光発電をめぐる技術と地域課題の諸課題をどう解決するのか?―
尾形清一(京都大学大学院 エネルギー科学研究科 准教授)
1.研究紹介
私はエネルギー工学・フィールドワーク(人文社会科学)・社会実装(政策デザイン)の三本柱を統合的に研究している。再エネ講座所属時は特にソーシャルアクセプタンスに着目していたが、エネルギー科学研究科の大半は工学関係の研究者であり、その影響もあって現在はシミュレーション実験や地域碑益を目指すカーボンニュートラル技術の開発をおこなっている。
シミュレーションについては、再生可能エネルギーシステムの定量的評価と政策への応用研究をおこなっている。例えば、計量的政策分析(DID)を使った地域エネルギー計画評価の研究やエネルギーシステムに関する数理モデリング、CO₂排出の多次元指標解析(国際比較)などをおこなっており、これらの研究成果は『Applied Energy』や『Energy and Buildings』、『Solar Energy』、『Sustainability』などの国際的なジャーナルに掲載されている。エネルギー科学研究科ではこのような国際的なジャーナルへの掲載が重視されている。
2.「より良い」地域再エネのための政策デザイン論
本日は、主にフィールドワークと社会実装に関して報告する。日本の再エネ研究者の多くはヨーロッパ寄りである。しかし、私はエネルギー科学研究科に来て以来、東南アジアの再エネに非常に注目するようになった。なぜなら、東アジアの文化・自然を考えると、東南アジアの再エネのあり方やコミュニティは日本の再エネ、特に地域再エネに対し重要な示唆に富んでいるためである。
まず、そもそも地域再エネとは何かということついて説明する。現在、私はさまざまな研究支援を受けて、東南アジア、タイで再エネコミュニティビジネスをやっている方々にヒアリングをおこなっている。私が地域再エネのビジョンとして理想形だと考えているのは1:再エネ(太陽光/太陽熱・バイオマス)、2:Local Grid(自営線/直流)、3:デマンドレスポンス(建築物省エネ・AutoDR)、4:グリーンな食料生産と「地域農業の六次産業化」、5:Well-Being(条件不利地域での地域雇用の創出)である。私が着目しているタイのある地域では食料自給・エネルギー自給に加え経済の自立性を志向するコミュニティデザインを成功させている。はじめは再エネユートピアコミュニティなのかと思っていたが、かなりしっかりとした取り組みがなされている。例えば、この地域は50世帯ほどのコミュニティであるが、送電網が来ておらず、電力系統に関しては陸の孤島状態である。そのため、ローカルグリッドを通じてエネルギーをコントロールしており、場合によっては直流で電力を使っている。また、建築物の省エネ化を通じたデマンドレスポンスに加え、陸の孤島ではあるが情報技術をフル活用してAutoDRにも取り組んでおり、見た目は田舎であるが非常に革新的である。さらに興味深い点は食料生産と再エネを結び付けている点である。グリーンで持続可能な食料生産に取り組んでいるが、グリッドにつながっているため売電はしていない。この取り組みの資金源は食料生産と地域農業の六次産業化であり、地域の経済的な自立性強化を目指している。そして、私が一番重要だと思っている点でもあるが、このような食料・エネルギー・経済の自立型志向コミュニティづくりになぜ取り組んでいるのかと聞くと、地域の人はWell-Beingのためであると明確に回答していた。この地域は南部にあるバンコクとは異なる北部の地域であるが、条件不利地域で雇用を創出することが念頭に置かれており、特に地域周辺に住んでいる女性の支援に非常に力を入れている。非常に生き生きとした地域であり、その中で再エネが上手に使われている印象を受ける。
私はこのような食料・エネルギー・経済の自立型志向にWell-Beingを加えたものが再エネの究極の理想形だと考えている。ただし、エネルギーシステム全体像をみて分析する立場から見て、この究極の理想形が全体最適につながるかどうかは別問題である。私が常に悩んでいるのは地域再エネ研究のひとつの特徴でもあるが、部分最適解としては素晴らしい構造にはなるが、その部分最適解を他の地域に広げた場合、それが全体最適になるのか、ということについてであり、この部分にはギャップがあると考える。私の研究関心はこのギャップを考えることである。つまり、生き生きとした再エネコミュニティをつくるための研究ではなく、そのコミュニティがマクロ政策の中でどのように位置づけられるべきかを考えることに関心がある。リサーチクエスチョンとしては、電力市場改革が再エネの理想形やWell-Beingにどのような影響を与えているのか、または、Well-Beingを実現する政策デザインとは何か、である。
また、私は東アジアの文化(価値観)を踏まえた「持続可能な社会構築」に関する研究に取り組んでいる。伝統のある分野ではあるが、私は少し異なるアプローチをとり、コーポレートサステナビリティのガイドラインのような研究をしており、地域再エネを持続化させるためにはどのような政策基準があるのかを研究している。その際に注目しているのがタイの「足るを知る経済哲学」とコーポレートサステナビリティの関係である。
コーポレートサステナビリティについてはTCFDやESG投資などさまざまなものがあるが、これらはヨーロピアンナイズされたコーポレートサステナビリティである。しかし、タイ・東南アジアには東アジア独特の哲学があり、私は東アジア風のコーポレートサステナビリティの基盤となる「足るを知る経済哲学」とビジネスの関係に注目して研究をしている。
足るを知る経済哲学は英語ではSufficiency Economy Philosophy(SEP)となる。タイは仏教国であり、仏教思想の中道や中庸の考えを政策デザインに織り込んでいる政策デザイン論と考えて問題ない。SEPは経済哲学の中の潮流で取り上げられてきたという意味では伝統があるが、私の注目点はこの哲学が『The national economic and social development plan』のような制度に文化として埋め込まれている点である。このようなことが起きているのは、タイの前国王であり国民からの支持が厚かったラーマ9世が、タイの新しい経済成長のあり方としてSEPをベースとしたためである。私はこのSEPがサステナビリティや地域再エネにつながっていると考えて研究に取り組んでいる。例えば、SEP志向のツーリズムで農村地域を支援する観光関係企業とのワークショップを開催し、Well-Beingや女性へのサポートに注目している研究者やバンコク有数のホテルのオーナーなどの現地の多様な方々と協力して研究を進めている。また、昨年にはタイのNational Institute of Development Administrationの国際会議にて、タイの地域再エネ企業の持続可能性の評価に関する研究で受賞することができた。この研究はタイの農業研究の大家である河野泰之先生にもご協力いただいた。このこともあり、東南アジアの地域再エネ研究への意欲が私の中で高まっている。
20年以上前からヨーロッパの地域再エネ研究に興味があり、私の修士論文はスウェーデンのシュタットベルケについてであった。しかし、エネルギー科学研究科に来てからはASEANとの関係がとても増えて、アジアの研究に取り組むようになった。そして、アジアの研究をするなかで、ヨーロッパではなく、意外にも東南アジアの再エネが日本に合うのではないのか思うようになった。アジア的な複雑な自然環境やコミュニティ、社会関係の中で地域再エネにどのように取り組むのかを念頭に置きながら政策デザインを組んでいる。私は地域再エネを技術の面から考えることについてはもちろん興味はあるが、それ以上に地域再エネの目的であるWell-Beingや地域の持続性をどう実現していくのかに関心がある。
本日報告する営農型太陽光に関してもMDPIのBest Paper Awardをいただいている。また、私は農村だけでなく都市の研究もおこなっている。現在は京大の学内選抜資金に採択され、都市の太陽光や脱炭素の研究をしており、こちらはペロブスカイト研究に携わっている若宮先生と共同でおこなっている。
3.営農型太陽光発電に関する研究
続いて、本日の本題となる営農型太陽光発電について報告する。営農型太陽光発電(Agrivoltaics)とは同じ土地で発電と営農を同時におこなう取り組みである。営農型太陽光発電は近年になって急増しているが、その先陣を切ったのは日本である。しかし、その起源はドイツであり、1980年代にはフラウンホーファー研究機構のソーラーエネルギーの研究論文にこのコンセプトは掲載されていた。
営農型太陽光発電では太陽光パネルの下で農作物を栽培するが、科学的なエビデンスを集めてシミュレーションをすると、遮蔽された条件でも多様な農作物を栽培できることが証明されている。太陽光パネルは思っている以上に農業の妨げにならず、トラクターもパネルの下を通ることができる。日本の農業は化石燃料で動くトラクターを使用しているが、今後はゼロカーボンのために電化されていく。太陽光パネルのエネルギーでトラクターを動かせるようになれば、ゼロカーボンの農業を実現できるのではないかと考えている。
日本の営農型太陽光発電の許可が下りたのは2012年頃である。営農型太陽光発電のスキームを使うことで第1種農地の転用が可能となる。第1種農地は農業以外の利用は認められておらず、太陽光パネルの設置は目的外にあたる。しかし、農業法でなく政省令を変える方法で一部転用が認められるようになった。ここは興味深い点であり、政策デザインとして重要な部分である。3、4年前に私が国際会議で発表をしていた時には、日本で営農型太陽光発電がどんどん増えているという話をよく聞いたが、現在はヨーロッパ各国の方が増えているように感じている。
一般的に認知されている営農型太陽光発電設備に加え、新しいタイプの発電設備が現れてきている。例えば、追尾型営農型太陽光発電はフレキシビリティを発揮することができる。パネル角度を遠隔で自由に調整することができ、電気が必要な時や市場で電気が必要な時は発電量が増える方向に調整される。また、このフレキシビリティは農業に対しても発揮する。農作物成長に光が必要な時期は限られており、パネル角度を調整して光の量を調整することができる。
また、垂直型の太陽光パネルの利用も増加している。一般的な太陽光パネルは12時台や13時台がピークとなるが、垂直型の太陽光パネルのピークは朝や夕方であるため、残余需要が小さいときに発電がおこなわれる。これは設計デザインのフレキシビリティと捉えることができる。また、ドイツなどの大規模農業がおこなわれている国では、大規模農業機械が使われるため垂直型の太陽光パネルは有用である。また、ヘテロ結合型の両面太陽光パネルの場合、通常のシリコンパネルと異なり、光の波長体が少し低い朝日や夕日の時でも発電量が多い。しかし、日本では太陽光パネルを立てる間隔が狭いため、本当に農業にとって良いのかは疑問が残る。そして、ヨーロッパの論文ではしばしば言及されているが、日本で実装する場合は風の問題を考慮しなければならなく、垂直型の太陽光パネルについては課題が多く残っている状態である。ヨーロッパの発想は非常に進んでいるとはいえ、日本や東南アジアの自然・文化にダイレクトに接続できるかというとそれは難しい。だからこそ地域再エネ研究に意味があり、私は国外の発想を日本型にローカライズする方法を研究している。
営農型太陽光発電のパネルは系統や構造、建設方法などで様々な類型があり、栽培している作物も多様である。また農業に限らず、陸上養殖や植物工場といった事例もある。藤棚式の太陽光パネルに注目が集まりがちだが、地域やマネタイズするスキームによって太陽光パネルの構造は異なる。営農型太陽光発電はデザインについてもフレキシブルにするべきである。
日本の営農型太陽光は、「農業用地を活用すれば太陽光をたくさん導入できる」という文脈で語られているが、私はこの考えに強い嫌悪感を抱いている。私は京都府の環境審議会の委員でもあるが、営農型太陽光発電を進めるという話になると、環境保護に熱心な方々は、「農地をすべて太陽光パネルで埋め尽くす」というような議論をする。日本では太陽光を導入するスキームと捉えられがちだが、諸外国では緩和策でなく、適応策として営農型太陽光発電が使われている。この点は日本ではあまり紹介されていない議論であるが、適応策として利用する利点のひとつは乾燥軽減である。営農型太陽光発電は農業利水を増加させるという論文報告が山ほどある。しかし、インドやタイの大学と営農型太陽光発電の研究をしたところ、発電設備により遮蔽されるため、効果としては水を抑える効果の方が高い結果となった。このほかにも作物に対して高温や過剰日射障害を抑制する効果が期待されている。
営農型太陽光発電の理論的な課題は、食料安全保障とエネルギー安全保障のトレードオフが存在する技術システムであるということである。発電量の比重を大きくすると、食料生産にはマイナスに働く。反対に食料生産の比重を大きくすると、発電量にはマイナスに働く。私はこのトレードオフをどのように克服するかが、普及や正しい実装に対して重要だと考えている。営農型太陽光発電はきちんと取り組めば非常に良いスキームであるが、先ほどお話ししたように農地を太陽光パネルで埋め尽くす議論をする人たちがいる。すると、当然ではあるが保守派の政治家や農業を大事にしている人たちから、「なぜエネルギーのために農地を潰すのだ」という声が出る。本日は報告することができないが、私はこのトレードオフを解決するためにGISを活用したアプローチをしており、最適なパターンを模索している。
農水省の「営農型太陽光発電設置状況等について」を確認すると、観賞用植物(さかき、しきみ、せんりょう、たまりゅう)の栽培が増えていることがわかるが、私はこれは非常に良くない事例だと考えている。なぜなら、観賞用植物が増えても食料安全保障に貢献しないためである。さかきやしきみが増えているのは、これらは光が無くても育ちやすい耐陰性の高い植物であるために世話がしやすいのに加え、市場では高値で取引されるためである。理想は、米や麦、大豆、そばなどのカロリー・たんぱく質自給率に貢献する農作物の栽培である。現状では、太陽光発電に加えて、付加価値の高い作物のみを栽培するという歪な構造になっており、この点も重要な問題として考えなければならない。
私は食料安全保障とエネルギー安全保障のトレードオフを解くという視点で、営農型太陽光発電のポテンシャル評価に取り組んでいる。私の考えとしては、遊休農地・耕作放棄地で営農型太陽光発電をすることが理想である。第1種農地でも条件によって営農型太陽光発電に取り組むことが可能だがリスクが高いため、耕作放棄地のような使われていない土地で取り組むべきである。数年前に私は研究室の学生と伊根町で現地調査をおこない、GISも活用して営農型太陽光発電を導入できる遊休農地を推定した。その結果、多くの遊休農地が活用できることが明らかになった。また、この研究では農地で大豆を生産すると仮定してシミュレーションをおこなった。大豆を選んだ理由は、大豆には農業がなされていない土地の土壌を改善する効果があるためである。結果は、LAOR(Land Area Occupation Ratio、土地被覆率、遮光率)を大豆生産を80%以上に維持できる35%に抑えても、遊休農地で営農型太陽光発電をするだけで年間総電力消費量の2倍以上の電力を確保できる結果となった。また、年間発電量(21,010MWh/年)や売電収益(2億3000万円/年)についても十分な結果が算出された。そして、内閣府のRESASを活用し、生産した大豆を伊根町の漁業養殖用のエサに利用した場合の地域経済効果も算出した。これらの詳細は中田秀樹氏の修士論文に掲載されている。
最後に、国内での食料安全保障とエネルギー安全保障のトレードオフ克服のための視点をまとめる。まずは、荒廃農地での利用を最優先することと、荒廃農地の再生が可能な「作付け・農法」を検討することが必要である。また、議論が分かれるかもしれないが、売電事業でなくセクターカップリング等に貢献する事業デザインも必要である。余剰については域外のマーケットで売ればよいが、地域内でのエネルギー消費を重視した方が良いというのが私の見解である。例えば、農業電化や地域EV、VEMS(Village Energy Management System)などの方法があるが、農業地帯を核としたエネルギーと食料の広範なシステムを構築することが必要だと私は考えている。そして、kWhは地域で消費し、カーボンクレジットが英国のようにしっかりと成り立っているのならば、環境価値はカーボンクレジットの利用が理想的だと私は考えている。最後の点としては、脱炭素農業ブランドの形成が挙げられる。ヨーロッパではゼロカーボン農業が進んでおり、炭素を多く排出した農産物はEUには輸出できない状態である。日本も農業生産の脱炭素を進めなければ輸出は不可能となるため、それを見据えた脱炭素ブランド化や六次産業化に取り組まなければならない。ただし、現状では日本の食料自給率がかなり低下しているので、その対策を考える方が重要かもしれない。
報告後のディスカッションでは所属を問わず、多様な研究会メンバーによりディスカッションがおこなわれた。特に、日本の営農型太陽光発電の事例(匝瑳市)の特殊性や、農業関係者との協調・コミュニケーションの必要性、営農型太陽光発電を取り巻いている制度的なリスクなど、日本における営農型太陽光発電普及の障壁についてディスカッションがなされた。