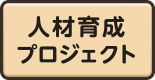2025年 6月27日(金)研究会 議事録
第2回研究会
2025年6月27日 15:00‐18:00
於:京大吉田キャンパス本部構内「法経東館」地下 1 階 三井住友銀行ホール
登壇者:小宮山涼一先生(東京大学)※オンライン登壇(科研費研究会共催)呉欽華先生(京都大学)
第2回研究会では、前半では東京大学の小宮山先生から、現在電力システム改革の方向性の一つである同時市場制度についての詳解がなされた。後半では、地域再エネ共同研究プロジェクトの呉先生より、先行研究レビューの報告がなされ、今後の取り組みについての議論がなされた。
「電力需給の最適化に関する動向」
小宮山涼一先生(東京大学)※オンライン登壇(科研費研究会共催)
本日は電力需給の最適化に関する動向を報告する。同時市場が検討され始めた背景と、同時市場の全体的なコンセプトと基本的な要素とロジック、そして現行の日本の電力市場の制度(特に再エネ支援制度)とどう関わるかを述べる。ただし、同時市場は検討が進められてる最中で、今回述べるのは私個人の見解。正式な情報は、各関係審議会の公表資料を確認されたい。
まず背景について。今後どう日本の電力市場制度を構築していくか。注目されている点は、中長期的な日本の全体での供給力確保である。供給力については、現在はFIT・FIP制や容量市場、長期脱炭素電源オークションで給力確保が行われており、今後どう改善していくかが重要である。また、中長期的な電力の取引をどう効率的に進めていくかも重要な課題。そして、短期的な市場制度をどう構築していくかも重要である。同時市場制度の導入は、特に短期的な取引を効率的に進めていくかという観点で、現在本格的に検討されている。
現在は、電力量(kWh)は卸電力取引所のスポット市場やベースロード市場で売買され、一般の事業者もベースロード電源を調達できる仕組みとなっている。ゲートクローズ後に追加で調整が必要になった場合には、需給調整市場で調整力(ΔkW)が取引される。短時間で需給を調整するための調整力(ΔkW)は、再生可能エネルギーの普及とともにニーズが高まる重要なリソースである。かつてはエリアごとに送配電事業者が「調整力公募」で確保していたが、現在は需給調整市場で競争的に調達する方式へ移行している。
「同時市場」は、電力量(kWh)と調整力(ΔkW)を同一の市場で同時に約定させる構想である。これにより、発電機の起動停止や出力配分を一括して最適化でき、調達コストの低減と供給信頼度の向上が期待されている。 ロジックの話に戻る。電力分野で「起動停止計画問題」や「電力需給シミュレーター」といった名称で呼ばれるものを使用している。入力データとしては、日本全国の基幹系統および上位2電圧の系統データ、需要データ、再エネ発電に関するデータ、スリーパートオファー情報を用いる。目的関数は、燃料費や起動費を最小化することに設定される。また、制約条件として、送電線の容量制約、調整力に関する下限制約、電源ごとの起動特性などの技術的制約が考慮される。これらの条件のもとで費用を最小化し、電源のラインナップや出力配分を決定していく。現状の検討においては、電中研のモデルや東京大学の電力需給最適化モデルが用いられている。また、最近の論点としては、送電ロスを最適化モデルに組み込む取り組みが進められている。
また同時市場は、需給調整市場における調達の見通しの悪さの解消も期待されている。需給調整におけるΔkWの調達は、再エネと密接に関連し、将来的には系統の混雑管理がより重要となる。系統制約を考慮しつつ最適に調達を行うロジックも導入する予定であるため、再エネが大量に導入された後の地域間および地域内の系統混雑の管理においても期待される。
現在の制度と異なる点としては、スリーパートオファー(起動費用、最低出力コスト、燃料費(増分費用カーブ))などの情報を、各電源単位で入札時に提供してもらうこととなる。これらの情報を基に、最適化ロジック(SCUC、SCED)を回すこととなる。小売側についても、必要な需要量と価格情報を予め登録してもらい、それに基づいて最適化ロジックを回すことになる。送配電事業者においても、必要に応じてΔkWを調整力として活用する運用が求められる。
入札義務も、現行制度と異なる部分を含む。発電事業者は、原則としてkWおよびΔkWの双方に対して、発電余力の全量を入札する義務を負うこととなる。また、需給逼迫等の状況に対応するために、同時市場においては電源情報を一元的に把握できる仕組みが設けられる。これは、各発電事業者が電源情報を正確に、かつ確実に提出する義務を負うことを意味し、この点も現行制度と異なる。
また、自己計画電源に関する仕組みも検討されている。現在の日本の電力取引の大部分は相対取引で、これが各事業者の予見性を確保している。同時市場においても、この相対取引を可能とするような電源運用オプションを用意する必要がある。このような電源は「自己計画電源」と呼ばれる。自己計画電源においては、発電側が自ら電源の起動および出力量を確定させる方式を採用する。
電源の起動に伴う費用の取り漏れを補填する「アップリフト」という仕組みも検討されている。最適化の過程で市場価格が決定されるが、この価格はシャドウプライス(需給均衡点での限界費用)に基づく。しかし、この価格だけでは起動費が回収されない場合がある。そのため、個別の支払いによって起動費の取り漏れを補填する措置が講じられる。これは、全体コストの中では大きくないものの、起動した事業者への正当な補償として、カバーされるべきである。これは海外の多くの市場で既に行われている。
「時間前同時市場」に関する検討も進められている。これは、前日から実際の需給時点までの間に、複数回SCUCを繰り返して実施し、発電側および需要側による取引を継続的に最適化していくもの。この仕組みは、世界においてもまだ実施されていない。
前日や時間前の最適化に加え、週間単位でも最適化を行えないかという試みもなされている。火力発電の中には、起動に長時間を要するものがあり、前日段階では有力な調整力候補にならないケースも想定される。したがって、1週間単位であらかじめ需給のひっ迫リスクなどを加味し、こうした起動に時間のかかる電源も市場の選択肢として取り込むことが重要である。ただし、再エネの出力変動を1週間前の段階で予測することは、現状では困難である1週間先の需給計画に対する予測精度を高めることも課題。また、揚水発電を含む電源の効率的運用においても、週間単位での最適化は極めて重要である。
最適化のロジックは、起動停止計画問題や電力需給シミュレーターと呼ばれるものを使用している。入力データとしては、日本全国の基幹系統および上位2電圧の系統データ、需要データ、再エネ発電に関するデータ、スリーパートオファー情報を用いる。目的関数は、燃料費や起動費を最小化することに設定される。また、制約条件として、送電線の容量制約、調整力に関する下限制約、電源ごとの起動特性などの技術的制約が考慮される。これらの条件のもとで費用を最小化し、電源のラインナップや出力配分を決定していく。現状の検討においては、電中研のモデルや東京大学の電力需給最適化モデルが用いられている。また、最近の論点としては、送電ロスを最適化モデルに組み込む取り組みが進められている。
「自己計画電源」および「市場計画電源」の入札についても述べておく。発電事業者が電源の起動および出力を自ら計画・申告する「自己計画電源」と、市場の最適化ロジックに起動・出力の決定を委ねる「市場計画電源(プール)」に電源は大別できる。
PJM等の事例をみると、原子力や流れ込み式水力発電のように出力調整が困難な電源は、その特性上、最適化ロジックによる出力制御が難しいため、自己計画電源としての入札が一般的である。これらは、いわゆるベースロード電源としての位置づけにあり、柔軟な運用が難しいため、自ら出力を決めて市場に参加する傾向が強い。
一方で、出力調整に優れた電源については、市場計画電源として運用されることが多い。これらの電源は、起動・停止や出力量の変更を柔軟に行えるため、すべてを市場の最適化に委ねることで効率的に運用されている。
全体としては、前日市場の段階において、約半数が自己計画電源、残りの半数が市場計画電源として構成されており、電源の運用特性に応じた柔軟な市場設計が行われていることがうかがえる。
再エネへの影響にも言及する。現在、FIT、FIP、コーポレートPPAなど、再エネ電力の調達手法が多様化している。この点についても、いくつかの方向性が想定されている。
FITについては、発電量を原則として買取義務者(小売または送配電事業者)が固定価格で全量買い取る制度設計が同時市場においても行われることが想定されている。FIPについては、再エネの出力量が前日同時市場から時間前同時市場、実需給市場にかけて変動する可能性があることを踏まえ、動的な対応が求められる。コーポレートPPAについても、市場に入札する方式や自己計画電源としての入札、市場外取引との連携(入札を伴わない市場外契約)などが考えられる。この場合でも、自社の出力予測量のみを市場に登録する運用が想定される。
また、揚水や蓄電池は、同時市場においても、市場計画電源として積極的に運用することが望ましい。特に再エネ導入の拡大を考慮すれば、電力貯蔵技術を柔軟に運用可能な形で市場に組み込む必要がある。揚水・蓄電池の最適運用と再エネの統合を両立させるためにも、kWだけでなくkWhの制約も含めた運用設計を行うことが、これからの重要な検討課題であると考えられる。
最後に、市場価格の決定方法についてまとめておく。これは現行制度と同様に、同時市場においても現在の仕組みを踏襲することが想定されている。
まず、スポット市場(kWh)においては、価格は基本的に約定結果に基づくシャドウプライスによって決定される。また、需給調整市場(ΔkW)については、機会費用(追加起動を必要とする電源に対するコスト)、起動費用、逸失利益(市場価格と各電源の燃料費の差分を)等をふまえて価格が算定される。これらの費用は、事前に登録されたスリーパートオファー情報をもとに、自動的に算出可能である。そのため、費用の提案・算定方法については、現行の需給調整市場と大きくは変わらないと考えられる。
ゲートクローズ後も、スリーパートオファー情報に基づいて、価格や選定が決定される仕組みが想定されている。なお、今後はシングルプライス制の導入が望ましいのではないかという提案もなされている。インバランス料金については、基本的に現行制度と同様の設計となる見込み。
制度やシステムが複雑化する側面は否定できない。日本においては、市場全体のトータルな設計思想や理念については、まだ十分に議論が進んでいるとは言い難い。今後は「どのような市場の姿を理想とするのか」といった根本的な問いについても、制度設計と併せて中長期的に検討していくことが重要であると考えられる。
質疑応答
【諸富先生】
一点目は、自己計画電源だと自ら申請したものについては、全体の最適化の外になるのか。二点目は、情報を各電力から提供していくということだが、戦略的に考えると、必ずしも正しい情報を提供しないかもしれない。本当に正しい情報を各電源が提供するのか。三点目は、再エネ電源が増えてきたときに、先ほど述べたように最適化を繰り返していくのが本当にいいのか。分散型決定に比べて、集権的な形での解決が望ましい結果になるのか。
【小宮山先生】
自己計画電源は最適化の外になると思う。原子力や石炭火力等出力調整次第しづらいものは差し引いた上で、残りを最適化するような形になる。自己計画電源の他に、LNGの燃料制約(受け入れ場の問題があるので、随時消費しなくてはならない)もある。あまり自己計画が大きいと、最適化しても価格の低減効果が得られず、市場の目的が達成できないかもしれない。これはちゃんと検証する必要がある。
情報の正確性については、監視する機能・体制整備することも大事。市場支配力のある事業者があまり正確ではないデータを登録するというのは間違いなく望ましい行為ではないので、監視をどうしていくかも検討を深める必要がある
費用については、どれぐらいコストの抑制効果があるかどうかの実証はなされてないが、系統の制約も考慮に入れて費用を下げられることなどから期待はできる。
【中泉さん】
一点目は、再エネの場合は気象条件も重要だが、ま、今回の最適化の中にうまく乗ってくるのか。2点目は、緊急時の予備電源も同じように最適化に乗ってくるのか。
【小宮山先生】
再エネと蓄電池は最適化の対象になると思う。事前に再エネ事業者には太陽光発電の出力予測をご入札いただく。
それから大規模災害に対する電源を同時市場でどう運用されるかはまだ検討されてない。今後具体化していった段階でそうした予備電源をどう位置づけていくかはおそらく議論になる。
【杉本先生】
新電力の目線を意識した質問をする。一つは、この同時市場が導入されたときにその計画値同時同量制度とかインバランス料金制度は変わらないのか。
もう一つは、同時市場は今の前日市場よりも約定のメカニズムが複雑になりそうということ。現状は前日市場だとオークションが終わった後にJPEXのホームページに約定カーブが公開され、誰がどう入札を入れたか、落札できなかった原因などがみえてくる。同時市場でも、約定の結果を視覚的に市場参加者に伝えることができるのか。
【小宮山先生】
インバランスは現行と同様の設計になると思われる。計画値同時同量については、計画値同時同量になるように出力配分がなされ、それの順守が求められる。
二点目については、系統制約も加味して最適化してるにも関わらず、結果については現在JPEXでやっているような需要曲線と供給曲線が交わる点から1単位増えたときの限界費用を利用するということが提案されている。落札が出来なかった場合には、系統制約がネックになって落札されない場合もでると思うが、そういったものの考慮した結果を見ることは難しいと思う。
【竹濱先生】
需給調整市場の調整力に風力がもっと増えた場合、同時市場ではどのような影響があるのか。
【小宮山先生】
実際、風力と蓄電池もある程度調整力にできる形で入札していく場合どうすべきか、まだ検討が多分なされてないと思う。海外PJMでは変動性再エネと蓄電池とか、ある程度リソースをアグリゲートして入札するということもやられているが、あまり送電線の距離が離れているしまうと、電力の潮流にかなり影響を及ぼす。なので、ある程度同じ地点に設置してあるものについては、変動性再エネと蓄電池アグリゲートした形で入札は認められてる。そういうことも日本でも検討すべきポイントかと思う。
「再エネの現状に関する調査」
呉欽華先生(京都大学)
今回は、先行研究をいくつかのテーマに分類して紹介する。全体のアウトラインとしては、まず再エネのポテンシャルに関するものは、日本を対象とした全国レベルの研究を取り上げる。風力発電については、特に洋上風力を扱う。風力発電の立地を巡る研究は、人文的観点からの分析が中心となっている。太陽光発電に関する研究では、太陽光発電の現状と応用、環境との関係、さらには設置拡大に伴う問題点についての研究を紹介する。また、近年問題視されている太陽光と風力のリサイクルに関する研究も紹介する。さらに、再エネ普及に向けた政策的インプリケーションに関する研究も紹介する。ここでは、政府主導・政策支持の重要性、コラボレーションの重要性、技術のスピルオーバー等について紹介する。最後に、電力システムの分析として、大規模の集中発電と分散型電力システムの比較分析や、バッテリー利用、地域エネルギーセキュリティに関する分析を紹介する。
まず、再エネのポテンシャルに関する研究を紹介する。Cheng et al.(2020)では、日本における再エネの賦存量を全国的に推計し、主に太陽光および洋上風力資源に焦点を当てている。これらの変動性電源の不確実性を補完するための水力資源も組み合わせて計算しており、その結果、日本の年間電力需要の14倍以上に相当する再エネ資源が存在するという推計結果が得られている。
洋上風力と太陽光発電を主な対象とし、シミュレーションによって分析している研究もある(Esteban & Portugal-Pereira, 2014)。特に、これらの変動性電源が電力システムに及ぼす影響と、それをどのようにバランスさせるかについて検討している。結果として、技術的には、2030年の日本において、再エネのみでも1人あたりの1時間あたりの電力需要を安定的に供給できる可能性があるという示唆が得られている。最後に紹介する研究(Yamaguchi & Ishihara, 2014)でも、前述の研究と同様の結論に至っている。
留意すべき点として、これらの研究はいずれも自然資源のポテンシャルのフル活用を前提に議論しており、経済的または社会的制約などを十分には考慮していない。すなわち、理論上は再エネのポテンシャルが非常に大きいとされるが、実際にどの程度の割合が導入可能であるのかという実行可能性の問題が、今後の大きな課題であると考えられる。
続いて、再エネ導入が漁業へ与える影響に関する研究について紹介する。大きな論点の一つは、洋上風力発電が魚の生産(漁獲)にどのような影響を与えるのかという点である。漁獲量に影響を及ぼし、漁師が伝統的な漁場から撤退する可能性が指摘される一方で、浮体式の風力タービンが漁場の構造物として魚群を集める装置のような役割を果たす可能性があるとの指摘もある。さらに、小規模の洋上風力発電であれば、漁業に与える影響が限定的であるとする研究も報告されている。
洋上風力発電が漁業に与える影響に関しては、多くの研究が間接的な影響にとどまっており、直接的な経済的影響を実証的に提示した研究はごく一部にすぎない。その背景には、経済データの不足や、経済的影響を定量化する分析やモデルの不足、総合的な情報の不足などがある。このような中で、一つの評価方法として注目したいのが、気候変動影響評価で用いられる脆弱性評価の手法である。これを地域スケールの空間情報に適用したもの(Helene et al., 2022)があり、空間的アクセスや時間的アクセスのほかに環境依存度・経済依存度・文化的依存度、物的資本・自然資本・人的資本・社会資本・経済資本といった観点から評価している。
また、洋上風力発電を他の産業と連携させるマルチユースについての分析もあり、風力発電所の周囲で養殖業や観光業を同時展開する取り組みが示されている。
風力の立地問題についての研究紹介に移る。今回紹介する2件の研究は、いずれもアンケート調査を用いた実証研究である。
1件目の研究(Ladenburg et al., 2024)は、洋上風力発電プロジェクトの新規設置に対して、住民がどの程度支払い意思を持っているかを明らかにしている。2件目の研究(Motosu & Maruyama, 2016)は、設置済み風力発電所による心理的影響を調べている。調査結果によれば、多くの住民は風力発電所の設置に対してストレスを感じていないと回答している。また、住民の多くが風力発電所に関する評判を聞いたことがなく、直接的なトラブルを経験した人も少ないことが示され、開発事業者に対する不信感も共有されていないという結果が得られている。直接的な接触が少ないことが、回答者の開発者に対する否定的な態度を増加させておらず、不信感の欠如が受け入れの増加に寄与する可能性があるとも考えられる。また、調査では風力発電所に対して高い期待を寄せている住民が一定数存在することも明らかになっている。
次に、太陽光発電に関する研究を紹介する。2020年時点のデータによれば、太陽光発電は国内の全電源構成のうち約3.6%を占めており、再エネの中では約31%という割合である。大規模な設備のみならず、家庭単位でも広く導入されているのも特徴である。特に、農業分野においても太陽光発電は広く活用されている。研究では、太陽光発電は、従来のエネルギー源と比べてより持続可能で柔軟なエネルギーシステムの構築が可能であることも示されている(Kumar et al., 2023)。
住宅用太陽光パネルの普及とその効果に関する研究(Vecchi & Berardi, 2024)はカナダの年次統計データを用いて実施されたものである。この研究によれば、住宅所有者が太陽光パネルの導入を選択した場合、戸建て住宅では約26%の電力消費量が削減され、集合住宅では最大で約7%の削減が見込まれるという結果が得られている。さらに、ネットメータリング対応型PVの導入効果についても分析されており、地域内の自給率が18%〜最大41%まで拡大する可能性があることが、シミュレーションにより示されている。こうした地域単位の導入を促進することで、グリッドへの依存度を下げ、エネルギーコミュニティの実現可能性を促進することも示唆している。
次に、太陽光発電および風力発電と環境との関係性についての研究を紹介する。まず一つ目の研究(Osman et al., 2023)では、気候変動の影響によって、再エネの発電量が変動する可能性について検討されている。風力発電や水力発電は、気象条件に大きく依存するため、最大で年間40%の発電量減少が起こる可能性があるとされている。また、バイオマス発電についても、気温上昇に伴って農作物の収穫量が減少し、それにより発電量が減少するリスクがある。一方で、地熱発電は地殻構造に依存し、気候変動の影響は限定的である。太陽光発電も、再エネの中では気候変動の影響が相対的に小さいとされている。
環境負荷に関する影響評価では、風力発電所が最も高い環境影響を持つ可能性があるとされ、太陽光発電においても、設置場所によっては自然環境や景観に与える影響が大きくなることが指摘されている。一方、陸上風力やバイオマス発電は、環境への影響が比較的抑えられると評価されている。
Hussain et al.(2023)では、「エコロジカル・フットプリント」を用いて、発電手法ごとの環境負荷を評価している。風力および太陽エネルギーが1%増加すると、エコロジカルフットプリントはそれぞれ3.1%および2.9%減少すると考えられている。
三つ目の研究では、地域間の送電能力や需要・供給バランスの調整力の有無が、市場価格の変動に与えている影響が分析されている。このような課題に対しては、地域間連系線の整備や揚水発電の活用などの対応策によって、価格の安定化が図れると結論づけられている。
再エネ拡大に伴うリサイクル問題に関する研究もある。風力や太陽光発電に用いられる材料のリサイクル体制が未整備であることは、将来的に大きな環境・経済的課題となる可能性がある。
再エネの推進に関連する政策的インプリケーションも多岐にわたって研究がある。政府主導の政策に焦点を当てた研究では、政府が風力発電事業者と漁業者との間に立ち、中立的な調整役を果たすことで利害対立を緩和した事例が紹介されている。また、政策の効果に注目した研究では、アメリカにおけるRPS政策が他地域へと波及するスピルオーバー効果が示されているほか、中国における再エネ産業の発展が、国内の技術イノベーションを加速させたことなども示されている。
政策実施においては、コラボレーションの重要性も指摘される。研究としては、CHRや、大規模な再エネインフラプロジェクトに関する研究などが行われている。
技術的観点に立つと、企業間あるいは地域間の連携が技術革新を促進し、再エネの開発や効率的なエネルギー利用に対して正の効果をもたらすことが示されている。さらに、技術のスピルオーバー効果に関する研究も進められている。また、分散型電源の導入が地域間あるいは所得階層間の利益配分に与える影響についても、中国における実証研究などが見つかる。
再エネの推進に関連する政策的インプリケーションも多岐にわたって研究がある。政府主導の政策に焦点を当てた研究では、政府が風力発電事業者と漁業者との間に立ち、中立的な調整役を果たすことで利害対立を緩和した事例が紹介されている。また、政策の効果に注目した研究では、アメリカにおけるRPS政策が他地域へと波及するスピルオーバー効果が示されているほか、中国における再エネ産業の発展が、国内の技術イノベーションを加速させたことなども示されている。
政策実施においては、コラボレーションの重要性も指摘される。研究としては、CHRや、大規模な再エネインフラプロジェクトに関する研究などが行われている。
技術的観点に立つと、企業間あるいは地域間の連携が技術革新を促進し、再エネの開発や効率的なエネルギー利用に対して正の効果をもたらすことが示されている。さらに、技術のスピルオーバー効果に関する研究も進められている。また、分散型電源の導入が地域間あるいは所得階層間の利益配分に与える影響についても、中国における実証研究などが見つかる。
最後に、エネルギーセキュリティに関する分析においては、単なる供給の安定性だけでなく、自給率、経済性、さらには生態系への影響といった4つの観点からの包括的な評価・分析も示されている。
以上の研究は、再エネ導入の実現において制度設計、技術、社会的受容、地域間連携といった多面的な要素が複雑に絡み合っており、それぞれが政策効果を左右する重要な要素であることを示している。その後のディスカッションでは、院生を中心に紹介内容や呉先生の関心兄用についての質疑がなされた後、会場・オンライン参加の先生・実務者を中心に、呉先生の今後の研究に期待される点などについてコメント・議論された。とくに・再エネ電源の社会的受容性・障壁(ハードル)とその超え方・洋上風力導入の波及効果に関する研究・海外事例を扱う場合の一般化 といったことについて議論が行われた。
Cheng, C., Blakers, A., Stocks, M., & Lu, B. (2022). 100% renewable energy in Japan. Energy Conversion and Management, 255, 115299. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2022.115299
Esteban, M., & Portugal-Pereira, J. (2014). Post-disaster resilience of a 100% renewable energy system in Japan. Energy, 68, 756–764. https://doi.org/10.1016/j.energy.2014.02.045
Hélène, B., Marjolaine, F., Christelle, L. G., & Le Floc’h, P. (2022). Vulnerability and spatial competition: The case of fisheries and offshore wind projects. Ecological Economics, 197, 107454. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2022.107454
Hussain, B., Asif Ali Naqvi, S., Anwar, S., & Usman, M. (2023). Effect of wind and solar energy production, and economic development on the environmental quality: Is this the solution to climate change? Gondwana Research, 119, 27–44. https://doi.org/10.1016/j.gr.2023.01.012
Ladenburg, J., Knapp, L. A., & Petrovic, S. (2024). Distance to offshore wind farms, onshore wind power spillover relationships, and the
willingness to pay for farshore, large-scale wind power development. Applied Economics, 1–17. https://doi.org/10.1080/00036846.2024.2392051
Motosu, M., & Maruyama, Y. (2016). Local acceptance by people with unvoiced opinions living close to a wind farm: A case study from Japan. Energy Policy, 91, 362–370. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.01.018
Osman, A. I., Chen, L., Yang, M., Msigwa, G., Farghali, M., Fawzy, S., Rooney, D. W., & Yap, P.-S. (2023). Cost, environmental impact, and
resilience of renewable energy under a changing climate: A review. Environmental Chemistry Letters, 21(2), 741–764.
https://doi.org/10.1007/s10311-022-01532-8
Yamaguchi, A., & Ishihara, T. (2014). Assessment of offshore wind energy potential using mesoscale model and geographic information system.
Renewable Energy, 69, 506–515. https://doi.org/10.1016/j.renene.2014.02.024
Kumar, Ch. M. S., Singh, S., Gupta, M. K., Nimdeo, Y. M., Raushan, R., Deorankar, A. V., Kumar, T. M. A., Rout, P. K., Chanotiya, C. S., Pakhale, V. D., & Nannaware, A. D. (2023). Solar energy: A promising renewable source for meeting energy demand in Indian agriculture applications. Sustainable Energy Technologies and Assessments, 55, 102905. https://doi.org/10.1016/j.seta.2022.102905