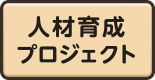2025年 5月30日(金)研究会 議事録
第1回研究会
2025年5月30日 15:00‐18:00
於:京大吉田キャンパス本部構内「法経東館」地下 1 階 三井住友銀行ホール
登壇者:諸富徹(京都大学公共政策大学院 教授)
第1回研究会では、地域再エネ共同研究プロジェクト代表の諸富徹先生より、プロジェクトの方向性についての説明及び大林財団による研究助成成果と山形県遊佐町沖の洋上風力発電の取り組みについて報告がありました。
1.「地域再エネ研での研究内容とその進め方について」
地域再エネ研は「研究プロジェクト」と「人材育成プロジェクト」の二つの柱で進めていく。研究プロジェクトの目的は、再エネ事業による地域経済波及効果の分析を通じて、再エネが地域発展や地域間格差の縮小にどのように寄与するのかを明らかにすることである。具体的には、合意形成に加え、再エネに関する地域再生/まちづくりに着目し、それを可能にするような再エネの大量導入をどのようにすればよいのかを考える。この点に関しては、かつて私が審査委員長を務めた環境省の「脱炭素先行地域」の考えに重なる。地域に再エネが導入・普及しそれで終わりということではなく、そこから地域経済循環の創出や地域課題の解決、次世代人材の育成につなげるということが重要である。このようなことを可能にするには、一定の利益を創出する核となる事業体を地域に設立するとともに、それを動かす専門人材を集めなければならない。しかし、給与や様々な機会で優位な東京で働きたい人が多く、地域にそのような人材を集められるのかという疑問は残っている。しかし、私が今まで出会ってきた方々のお話を聞くと、産業衰退と人口減少で衰退する地域を再エネで反転させることに対し一定の手ごたえを感じている人々も多数いることも確かである。研究プロジェクトとしては、そのような再エネと地域発展の好循環を生みだすにはどうすればよいのかを研究していきたい。
一方で、大量の再エネの普及ということに関しては、地域に碑益する形でないと進まないというのが現状である。再エネ設備が迷惑施設となっている事例も見受けられ、また、場所によっては逆風が吹いている状態である。例えば、宮城県では森林を切り開いて太陽光パネルを設置する場合は課税対象となった。また、法令上の規制や遵守すべきルールも厳格化している。研究プロジェクトとしては、厳格化している規制にどのように適合し再エネを受け入れ可能にするかという消極的な観点を超えて、地域再エネ事業が地域にプラスになるという点に焦点を当てたいと考えている。
再エネを増やしていくうえでの政策手段や電力市場の設計といった環境整備の研究は第2期で力を入れてきた研究だったが、今回は後景に退くこととなる。しかし、地域再エネを実施するうえで、電力市場の動向確認は不可欠であり、電力系統についても同様である。そのため、これらの分野についても引き続き動向を確認していく。
研究プロジェクトの進め方としては、月一回の定例研究会と年一回のシンポジウムの開催、DP(ディスカッションペーパー)のホームページ上での公表を想定している。DPは研究成果を論文化したものであるが、最終的な目標は学術誌への掲載とし、その前段階として位置づける。
本プロジェクトのもう一つの柱である人材育成プロジェクトについては、地域と関わり、社会のイノベーションを担っていける人材を輩出したいという考えであり、その素材として再エネを位置づけている。今年の9月1日には講義と交流会を含むワークショップを開催する予定である。ワークショップには日本風力開発社長の藤谷雅義氏に加え、諸富研究室出身であり、現在は飛騨高山で小水力発電に取り組む井上博成氏(一般社団法人CoIU設立基金)にご登壇いただく予定である。また、当日はパネルディスカッションも予定しており、キーリー アレクサンダー竜太氏(九州大学工学研究院)、丹野裕介氏(株式会社Sustech)、吉高まり氏(一般社団法人バーチュデザイン)のご登壇を予定している。そして、10月から12月にかけてインターンシップを実施し、実習先としては日本風力開発や井上氏が設立準備を進めている大学「Co-Innovation University(仮称)」のネットワークを活用した企業への派遣を想定している。その後、2月か3月にワークショップ登壇者と参加者が再び集まり、参加者はそれまで学んだことの調査・分析結果を発表し、それに対して登壇者がフィードバックを行う予定である。この人材育成プロジェクトは大学の修了要件とは関係ないため、何名の参加者が集まるかは未知数であり、挑戦的なプロジェクトになる。
2.「地域脱炭素化の主体としての地域新電力の可能性~大林財団による研究助成の成果~」
私は現在、地域で再エネを普及するうえで核となる組織としての地域新電力に関心を抱いている。地域新電力のモデルとされているドイツのシュタットベルケ(Stadtwerke)という組織は再エネを含むエネルギー事業で稼ぎ、その利益を地域公共交通事業などに還元している。シュタットベルケは再エネへの再投資も行うが、それでもなお余剰の資金が生まれている。様々な事業の株式を保有している上位団体であるシュタットベルケ(例えば、フライブルク・シュタットベルケ有限会社)は自治体100%出資の組織であり、エネルギー事業から得られる配当収入を活用して地域公共交通事業の運営補助をしている。このような事業スキームはシュタットベルケと呼ばれており、「シュタット(Stadt)」は都市、「ベルケ(werke)」は英語のworksにあたり、直訳すると「都市の事業」という意味である。シュタットベルケを通じて、ドイツはうまくエネルギー事業を地域の富に変えているのである。日本には大手電力・ガス会社が有力であり、それらに料金を支払うと所得が本社へと移転することとなり、必ずしも所得は地域に残らない状態である。この点に関して分散型の再エネの良いところは、地域が地域の電力事業に資本参加できれば配当収益の形で利益を得ることができ、それをさらに地域内へ再投資することが可能になる点である。日本全国をみると、このような取り組みが各地で始まっている。
本日紹介する地域は三つあり、一つ目の宮古市は、東日本大震災で甚大な津波の被害を受けた地域であり、津波被害のあった地区にメガソーラーをつくり脱炭素化を進めている。二つ目の山形県は、「2段階発展モデル」を採用している地域である。この事例は、事業ノウハウのない最初の段階は外部の力を借りて地域新電力を創設し、そして、ノウハウを獲得した次の段階で電力の需給調整を自身でおこなうようになった事例である。三つ目の北九州市は脱炭素先行地域として北九州市都市圏17市町と連携して脱炭素を進めている。
【1】宮古市版シュタットベルケの取り組み
宮古市は地域発電会社と地域新電力会社に参画している。宮古発電合同会社は日本国土開発(80%)、アジア航測(10%)、復建調査(10%)の出資により創設された。これらの民間事業者は復興を手伝いたいという思いから震災後に宮古市との間に協力関係ができ、津波の被害で更地となった田老地区に太陽光発電設備を設置した。後に宮古市も出資するようになり、現在の出資割合は日本国土開発(70%)、アジア航測(5%)、復建調査(5%)、宮古市(20%)となっている。宮古新電力についても設立当初は民間企業100%出資であったが、現在はNTTアノードエナジー(80%)、宮古市(20%)となっている。宮古市は2020年に固定資産税収入1億6,800万円を元手として「宮古市再生可能エネルギー基金」を創設し、これを事業への出資財源とした。地域新電力の利益は少ないが、発電会社の利益は自治体規模を考えると大きく、宮古市は約1,500万円の配当金を2024年度には得ている。現在、田老地区にて太陽光発電設備のさらなる設置を進めており、この配当金はさらに増える見込みである。
宮古市は電力事業から得る配当金を基金に積み立て、再エネへの再投資、地域公共交通の支援に活用しており、将来的には子育て、教育などの地域課題解決の財源としても活用するとしている。現在、宮古市は地域公共交通の維持という課題に取り組んでおり、基金を活用し、脱炭素先行地域の取り組みの一環としての路線バスの電気バスへの切り替えに加え、バス事業の運営補助をおこなっている。エネルギー事業の利益で赤字の公共交通事業の運営補助を行うのは、まさにドイツのシュタットベルケの方法であるが、経済学者からは内部補助として批判されることもある。しかし、ドイツで実証されているように公共交通を整備することで中心市街地は活性化することとなる。日本の自治体では富山市も公共交通整備により中心市街地が活性化しているが、それは地価の維持につながることとなる。地価が維持されると民間投資が活性化し、様々な商店が進出し、人口が吸引されることで都市のコンパクト化が進むこととなる。その結果、固定資産税収入が増加し、富山市でもLRT整備への投資分の回収が可能となっている。このような大きな枠組みで考えるか、または事業会計ごとの収支勘定をするかで、内部補助に対する見え方は変わるのである。
【2】山形県における、地域新電力を通じた地域脱炭素の全県展開
「やまがた新電力」は山形県と山形パナソニックなど民間企業17社が出資して2015年に設立された。特徴的な点は二つ挙げられ、第一の特徴が先ほど少し説明した「2段階モデル」である。新電力設立当初は、NTTファシリティーズ(現「NTTアノードエナジー」)に電力需給調整業務を委託していた。しかし、業務委託費負担の重さや事業の将来展開への制約などの観点から、需給調整業務などの新電力経営のノウハウや業務システムを中間支援組織から学び、2019年に内製化に成功したのである。
山形県の取り組みの第二の特徴は、民間でなく県が主導的な役割を担っている点である。やまがた新電力は県が出資する日本初の全県レベルの地域新電力である。山形県は「最上地域」「村山地域」「置賜地域」「庄内地域」という四つの地域に分かれており、それぞれの地域に地域新電力を設置するとしている。震災後、山形県は2度の停電を経験し、県民感情としてエネルギー自立の考えが強まり、また、原発事故の反省から再エネの取り組みが進んでいったのである。最初はエネルギーをつくることに力を入れ、県も電源開発に注力した。一定程度開発が進むと、ただ単にFITで売電するだけでなく、脱炭素のために地域再エネを地域で使い、資金も地域還流させていくということを考えるようになった。そして、それを担う存在として地域新電力が位置付けられた。しかし、県レベルで地域新電力が一社あるだけでは、広大な県での事業展開は難しいため、四つの各地域に拠点を置くという戦略をとっている。
【3】北九州市:北九州都市圏域17市町との連携
「北九州パワー」の電力販売先は基本的に北九州市と17市町の公共施設と中小企業となっている。電源については三分の一を市場から調達しており、残り三分の二は地域内の太陽光発電などもあるが、量的に最も多いのは北九州市所有の廃棄物発電施設からの調達である。廃棄物発電に関しては組成調査に従い、廃棄物中の何パーセントが再エネであるかを認定しており、例えば、食品残渣などを燃焼して作ったエネルギーは再エネと認定されている。
北九州市は脱炭素先行地域に認定されたこともあり、再エネの導入が進んでいるが、その動きは急速に加速している。その仕組はPPA(Power Purchase Agreemet)での再エネ導入である。PPAはリース会社が設備を設置するため、初期コストゼロで導入が可能である。もし、北九州市が全額経費で公共施設の屋根に太陽光パネルを設置する場合、莫大な予算確保が必要となるが、PPAの場合は自治体がリース会社と電力購入契約を結び、20年間設備費を含めた電気代を支払うスキームであり、負担が抑えられる。PPAの中でも若干割高になるものもあるが、これに対し北九州市では「総括原価」というシステムを採用している。このシステムでは、全公共施設のPPAコストを全公共施設の電力需要量で割り、kW当たりの価格に平準化される。その結果、kWあたりわずか0.1円の値上がりで済むこととなる。
北九州パワーの電力は市有の廃棄物発電を活用することで九電よりも安くなっている。これは、廃棄物発電施設を有することで相対で電力を調達でき、市場変動リスクを抑えることができるためである。また、北九州パワーは北九州市と協議を毎期重ね、市場価格より二割から三割安い価格での電力調達を実現している。北九州が低価格で北九州パワーに売電することに関しては疑問を抱く人もいるかもしれない。しかし、北九州市は廃棄物発電に加え相対や市場で調達する電気を北九州パワーから買うことで、最終的には九電よりも四割ほど安く電気を購入することが可能となっている。
設備の設置動向については、例えば、避難所を運営している部署には太陽光パネルを設置するとともに蓄電池を設置し、災害時の避難所としての機能強化も図っている。また、小中学校の場合は理科室や音楽室、給食の調理室などのエアコンの導入が進んでいない場所でのエアコンの導入と同時に太陽光パネルの設置を進めている。環境部局が脱炭素を推進すると言っても、最初は再エネ設備の設置は受け入れられなかった。そこで、近年の夏の酷暑で生徒が苦しんでいるという問題を挙げ、太陽光パネルと同時にエアコンを導入すればそれほどコストがかからないという提案をしたところ、理解を得たうえでの再エネの効果的な導入が実現した。
17市町向けには「取次型新電力」創設の支援に取り組んでいる。これは先ほどの、やまがた新電力の取り組みと類似している。例えば、ある地域の商店街の全店舗の脱炭素化を進めようとする場合、新たに新電力を設立するとなると資金や人手が必要となる。そこで、代わりに北九州パワーが顧客管理や料金徴収、電力供給を請け負うことで、商店街の連合会は新しい組織や人手を増やすことなく、業務の片手間で事実上の地域新電力業務をおこなうことが可能になる。このような形で北九州パワーは供給先を増やしており、利益も上昇している。また、中小企業に営業をかけているだけでなく、大企業にもアプローチしている。例えば、自動車工場に対しては、トランプ関税の影響で自動車の輸出が滞り、工場の操業度が下がると、それまで使えていた九電の大量使用者向けメニューが使えなくなり、九電よりも北九州パワーから電気を買った方がコストを抑えられると説明している。
3.「再生可能エネルギー事業と地域共生~山形県遊佐町沖洋上風力発電のケース~」
続いて、再エネが地域経済の発展に寄与することについて、遊佐町沖の洋上風力発電の事例を基にお話しする。遊佐町では洋上風力発電設備を30基ほど建設する予定であり、計画に関する合意形成プロセスはすべてホームページ上で確認することができる。遊佐町の事例は、海域利用法上の法定協議会ができるよりもかなり前の時期から、県が事前の協議会をつくり多くの困難を乗り越えてきた事例である。この事例に関わってきたのが第4回研究会にご登壇いただく槙裕一氏である。
合意形成における困難の大部分は漁業との調整であり、協議がなかなか進まない中、県が積極的に介入して協議を進めた。その時に話し合われたのが、現行の漁業が不可能になるならば、今後はどのような漁業をしていくべきかという点である。その方法としては、風車を設置する際に漁礁も同時に設置することが挙げられ、また、漁業基金の造成も挙げられた。この基金は積極的に新しい漁業を行うための準備資金としての性格を有している。法定協議会は複数の漁業組合を集めて合意形成を図り、将来の漁業像を取りまとめ、それを公募文書の中に入れて公募を行った。公募においては、この地域の声を最も取り入れた提案をした丸紅が選定されることとなった。
遊佐町の計画では、漁業協調策と振興策の二つに取り組むとしている。「協調策」とは、風車を海に立てることによって生まれる損失をゼロにもどす環境整備策を指す。「振興策」はそれにとどまらず、今まで以上に漁業をよくしていこうとする策である。これについては、地域における新産業の育成とそれに関連する雇用確保、電力の地産地消、人材育成、観光振興、港湾・漁村地域の活性化、地域住民の安心・安全な暮らしの実現、自然環境の保全、海洋環境への配慮などの多様な取り組みが挙げられている。
また、計画に関してはコンサル会社による経済波及効果の分析もおこなわれている。その報告書内では、自治体の総生産額に占める製造業、建設業の割合が示されている。これを確認すると、遊佐町の製造業の割合は19.1%となっており、全体の割合としては大きくないことがわかる。これは、風力発電事業が実施されても製造業に関する便益は大きくないことを示している。しかし、漁業と観光分野の活性化に加え、風力発電で生まれた再エネでグリーン水素生成し、周辺に位置する酒田港付近の産業集積地帯でそれを活用するプロジェクトを実施するということは可能性として考えられる。
以上のように、漁業組合がお金をもらうことと引き換えに事業を受け入れるのではなく、新しい漁業振興策を通じて地域再生を図っている点で遊佐町は興味深い事例である。本日は事例紹介にとどまったが、第4回研究会では現地の方々からこの事例についてお話を伺える予定である。
・報告後には、洋上風力発電事業収益のどれくらいが地域の基金に回されるべきかや地域新電力のデマンドレスポンス導入の可能性、FITからFIPへの移行で生じる問題への対応、下水道を活用した地域再エネ事業の可能性、地域再エネ事業における公共性など、幅広い議論がなされた。